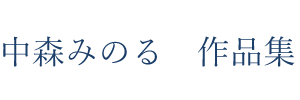(いつまでこの部屋にいればいいんだろ)
私はがらんとした病室を見渡した。それから、もう何度見たかわからない、愛犬ジョンの写真を手に取った。女の子と犬——つまり私とジョンが写っている。 ジョンは白いシーズー。ふさふさの毛がとってもかわいい。私は、写真立ての横にあったジョンと同じくらいの大きさのぬいぐるみを、ギュッと抱き寄せた。
(私の大好きなジョン。元気にしてるかな)
明るい夕日が差し込んでいた。開け放った窓が、カーテンを揺らしていた。
窓の外からは鳥たちの鳴き声が聞こえてきた。散歩を終えた患者が、看護師に付き添われながら、ゆっくりと入り口の方へ歩いている。
でも、この個室にやってくるものはいない。最初の内こそ見舞いに来てくれていた友達にも、もうずいぶん会っていない。
私は、ふと廊下の方へと目をやった。すると、不思議なことに、廊下の向こうに人影が見えた。
「だれ?」
人影は、こちらへゆっくりと近づいてくる。
私は、見覚えのないその人影に、思わず目を凝らした。ちょうど私くらいの背の高さだ。
(もしかして、同級生の誰か?)
じっと見ていると、なおも人影は近づいてきた。姿がだんだんはっきりとしてくる。
ところが、その姿を見て、私は思わず息をのんだ。私にそっくりだったからだ。
「だれ? だれなの?」
返事はなかった。青白い顔をして亡霊のように立っているその子は、まるで写し鏡の中の自分のように、この世のものとは思われないものを見ているかのような、こわばった表情だった。
(ドッペルゲンガー……!)
私は、ある伝説を思い出していた。ドッペルゲンガーという、自分そっくりの存在が、世界のどこかにいるという伝説だ。その姿を二度見たものは、死んでしまうという。
(……そう。もう長くないのね)
私の病気は、どれくらい進行してしまっているんだろう。もう、お別れの日が来てしまうんだろうか。
「あなた、ドッペルゲンガー?」
ややあって、私そっくりの人物がうなずいたように見えた。
こんな不思議な体験をしたことがなかったからだろうか、本当なら恐ろしいはずなのに、恐怖よりも好奇心が勝っていた。
「そう。それじゃ、あなたは私ってわけね」
ドッペルゲンガーがうなずいた。
私はまじまじと、私そっくりのドッペルゲンガーを見た。思わずちょっと手を伸ばした。でも、触るのはさすがにためらわれる。もう一人の自分は、じっとこちらを見つめている。
「私、もうすぐ死ぬの?」
私は、じっとドッペルゲンガーを見た。だが、彼女は何も言わず、こちらを見返すだけだ。
「それなら一つ、お願いがあるの。ねえ、どうしても聞いてほしいの!」
ドッペルゲンガーは黙ったままだ。私は、話し始めた。
「あなたが私なら、うちにいるジョン、知ってるでしょ? シーズーのジョンよ」
すると、ドッペルゲンガーはうなずいた。
「あの子と一緒に、もう一度散歩に行きたいの。ね、おねがい! 一緒に散歩に行ってくれない? お願いよ!」
私の体の中のどこに、そんな勇気と力があったんだろうか。ジョンのことを考えると、いてもたってもいられなくなって、とうとうドッペルゲンガーにすがりついた。
ドッペルゲンガーは、こわばった表情のまま、静かにうなずいた。私は荒い息のまま、ベッドに体を戻した。
「お願い……お願いだから、一緒に散歩してあげて」
ドッペルゲンガーは、力強くうなずいた。彼女は腰をかがめると、何かを手渡した。お守りだった。
それから後も、私のことをしばらく見つめていたが、やがて音もなく、病室を出て行ってしまった。
全身から力が抜けていくのを感じた。
(ドッペルゲンガー……あんな存在が、本当にいたんだ)
私は、白昼夢か幻でも見ていたのかと思ったけど、ふと手の中を見ると、ちゃんとお守りがあった。健康祈願のお守りだった。
◇
翌日。
夕方になるのを、私はずっと待っていた。
(ドッペルゲンガーが、またやってきてくれるかもしれない)
2度見たら死んでしまうといわれているらしいけど、不思議とそんな気はしなかった。
それに、やがて死んでしまうということは、もうわかっている。それよりも、ジョンが元気にしているかどうか、それだけが心配だった。
(ゲンガーちゃん、ちゃんとジョンと散歩してくれたかな?)
その時、廊下に影が現れた。ドッペルゲンガーだった。
もう一人の私は、静かに近寄ってきた。手にはビデオカメラを持っている。
もう一人の私は何も言わずにベッドに座ると、ビデオカメラの映像を流し始めた。
「ジョン!」
画面にジョンが映っていた! ジョンはちぎれんばかりに尻尾を振って、大喜びで散歩をしている。
「ジョン……」
私はうれしくなって、ゲンガーちゃんを抱きしめた。
「ありがとう、私の代わりに散歩してきてくれて……ほんとうにありがとう!」
涙が落ちた。ゲンガーちゃんの肩が濡れた。ゲンガーちゃんは、ゆっくりと私の体を起こすと、ビデオの続きを見せてくれた。
ジョンは、あちこちながめながら歩き、ゲンガーちゃんはそれに合わせて歩いていた。突然ジョンが走り出した。ゲンガーちゃんも、負けじと走り出し、画面がぐらぐら揺れた。 走り終えると、二人は座り込んだ。ジョンは、草っぱらに鼻を近づけ、ふんふんにおいをかいでいる。そうやってかぎまわっているうちに、不意にカメラの存在に気がついた。こっちに近づいてくる。ジョンの顔が、大きく画面に映し出された。私は、じっとジョンと見つめ合った。
「ジョン……」
ジョンが画面をなめ始めた。私は、画面に頬を押し当てたい気持ちにかられながらも、ただ熱にうなされるように、じっとその様子を見ていた。
ビデオが終わった。私は気持ちが高ぶったせいか、どっと疲れを感じてベッドに横たわった。
「ありがとう……私、とっても嬉しい。ほんとにありがとう」
夢の世界へと入っていく私を横目で見ていたゲンガーちゃんは、スーッと立ち上がった。そして、そのままゆっくりと、病室を出ていった。
私の目は、そのまま閉じられた。
◇
病室を出たドッペルゲンガーは、目に涙を浮かべながら、そっとつぶやいた。
「また来るからね、お姉ちゃん。私の体があれば、きっと治るはずだから」