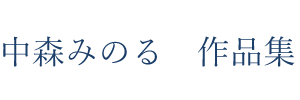10月21日、放課後のことだった。
少し雨が降っていて寒かったが、渡はいつものようにモコに会いにいった。夕日は沈みかけ、もうすぐ夜になりそうだ。渡は広場へ急いだ。
「ミャー」
突然道の途中で、草むらからモコが出てきた。
広場はまだ先だ。モコが広場より先の道に出てくることはないはずなのに。ずっと渡を待っていたんだろうか、びっしょり濡れている。
「どうした? 何かあったのか?」
モコはふるえながら、力なく近寄ってきた。渡は首で傘をはさんでからモコを抱き上げると、広場のほうに行こうとした。ところが、モコはおびえた様子で嫌がった。広場でなにか嫌な目にあったんだろうか?
渡はちらっと広場の方に目をやった。
「なにも変わってないじゃない」
と、その時、茂みががさごそいって、何かが森の方に逃げていった。良く見えなかったが、しっぽらしきものがちらっと見えた気がした。たぶんトカゲかなんかだろう。ところが、モコはびくっとそちらを見て、渡にすり寄ってきた。
「どうした? ただのトカゲだよ」
ところが、モコはすっかりおびえた様子で、渡の体にすり寄ってきた。体の震えが尋常ではない。寝ている間に、トカゲに鼻でもかみつかれたんだろうか?
少しためらったものの、渡はモコを抱いたまま、家まで連れて帰ることにした。こんなことは初めてのことだ。
両親は共働きで、家には誰もいない。玄関に入ると、ひとまずモコを軽く濡らしたタオルできれいに拭いた後、かわいたふかふかのタオルで乾かした。
モコは体をふかれているうちに少しずつ落ち着いたのか、それとも寒さが和らいだのか、体のふるえも止まった。渡は、自分の部屋にモコを連れていくと、クッションの上にモコを置いた。すぐに部屋のカギをかけた後、モコのトイレを作ることにした。あまっていた段ボールの中に、古新聞を何枚も細かくちぎって入れる。これが簡易のトイレになった。
「モコ。いざってときは、ここでしてくれよ」
モコはだまって渡をじっとみた。渡はモコの首にだきついて、頭をなでた。
もうあたりはすっかり夜。モコを帰すのは難しそうだ。そのうちお母さんが、それからお父さんも帰ってきた。部屋の常夜灯だけつけておくと、ご飯を食べに降りた。渡はご飯を食べながら、モコを明日の朝広場に返すことに決めた。
部屋に戻ると、モコはおとなしくしていた。緊張させてしまったのか、トイレをした様子もない。
「大丈夫?」
すると、モコはニャーと小さい声で鳴いた。渡はふふっと笑った。
(小屋を作ると安心するかも)
渡はふとんを床におろすと、小さな洞窟をつくった。そこにはいっていると、モコが近づいてきたので、抱きあげて膝に乗せた。雨はいよいよ強く降っている。
それにしても、いったい何があったんだろうか? だれかにいじめられたんだろうか?
だが、それは考えにくかった。あそこに人は来ないし、モコも警戒して出ていかないはずだ。トカゲにびっくりしていたが、トカゲなんてモコが怖がるはずがない。
だとしたら、野犬かカラスにでも襲われたんだろうか?
このあたりでそんな話は聞いたこともなかったが、ありえないことではないと、渡は思った。
(ひとまず明日、広場の様子を見よう……)
渡はモコをクッションに戻すと、上からふわふわの小さなタオルをかけて、布団を元に戻した。カーテンを少しだけあけたあと、ベッドの上に寝転んだ。
「おやすみ、モコ」
常夜灯も消してしまうと、渡とモコは、ぐっすり眠った。
翌朝、雨はすっかりやんで、空は晴れていた。カーテンの隙間から光が差し込んでいる。ふと、体の上に、何か重たいものを感じた。
「ニャ」
そうだ、モコを連れて帰ったんだった!
渡は体を起こすと、モコを抱き上げた。初めてモコと会ったときのことが思い出された。もうこんなに大きくなったんだなぁ……と、感慨深い気持ちが押し寄せる。ふとモコの寝床とトイレを見てみると、モコはちゃんとトイレでおしっこをしたらしかった。
「えらいぞ、モコ」
渡はモコをなでた後、自分もトイレを済ませ歯を磨き、パンを食べた。モコのトイレを段ボールごとゴミ袋にまとめ、制服に着替えた。モコは、その様子をじっと見ていた。渡は準備が終わると、かばんをしょって、片手にゴミ袋、片手にモコを抱いて、気づかれないよう家を出た。
「いってきまーす」
渡はゴミを捨てると、さっそく広場に向かった。モコは少し落ち着かない様子で、時々にゃーんと鳴いたが、とりわけ騒ぐこともなく、渡の腕の中にいた。
広場に着くと、昨日の雨で地面がぬれているほかは、特に変わった様子はなかった。地面におろしてやると、モコはふんふんとにおいをかいで、あたりの様子をうかがっていた。
渡は湿ったベンチに座ると、モコが落ちつくまで様子を見ることにした。ちょうどカメラも持ってきていたので、気まぐれに何枚か撮った。
しばらくすると、モコも落ちついてきて、渡のひざを離れ、あたりを歩き回るようになった。もう一時間目には間に合わない。もう少し早く起きればよかった。
「落ちついたか?」
モコに近寄って行くと、モコはニャーンとないた。いつもなら自然と森の中に入っていくのに、今日は入ろうとしない。だが、渡はその時、次の授業に間に合わせたいという気持ちでいっぱいで、そのことに気がつかなかった。
「じゃあ、もう行くからね。放課後また来るよ」
渡は朝ごはんに、特別ににぼしを多めにあげた。それから広場を出ていこうとすると、モコが食べている途中のにぼしを置いて、こっちにすりよってきた。
「どうした? 遅れちゃうよ」
モコを何度かなでてから、スッと立ち上がった。歩き始めても、今度はもう、モコは追って来ようとしない。広場の入り口まで来た時、気になってモコを振り返った。まだじっとこちらをみている。宝石のような、美しいまなざしだった。渡は、戻っていきたいような気持になったが、授業のことを考えて、学校に行くことにした。
学校に着くと、すでに二時間目が始まっていた。気まずかったが、仕方がないので後ろから入っていった。
「お、時野戸。また遅刻か?」
石丸先生がすかさず声をかけてきた。
「すみません、お腹の調子が悪くて」
「そうか。無理するなよ」
石丸先生はそれだけいうと、授業を始めた。渡は、それほど追及されなかったことにほっとして、授業を受け始めた。数学、英語、理科……そして、昼休みになった。
渡はお弁当を食べながら、どうも落ち着かない気持ちになっていた。
(モコ……。あいつ、大丈夫だろうか? もう少し一緒にいてやればよかった。なんだか不安そうだったし、もう少し家で様子をみてやったほうが良かったかも……)
渡はぐるぐる考えるうちに、次第にいてもたってもいられなくなってきた。渡が急にたべかけのお弁当をしまい始めたのを見て、友達の松田が驚いた。
「どうした? もしかして、まだ腹が痛いのか?」
「ああ。先生に早退するって言っといて」
渡はそれだけ言い残すと、広場に向かって走っていった。
広場はいつものように、しんとしていた。まだあれから3時間ほどしか経っていない。
(大丈夫、モコはいるはずだ。いつものように、森の茂みの中から、現れるはず……)
「モコ! モコ!」
じっと森の中を見ていると、茂みがガサガサいって、モコがひょっこり姿を現した。
「ミャー」
いつものようにモコを抱き上げると、渡はほっとため息をついた。
よかった。いつものモコだ。
「こいつ! 心配したんだぞ」
渡は、いつものようにモコと遊んで帰った。
それから一週間、モコに変わった様子はなかった。
ところが、ある朝のこと、事件が起こった。いつものように広場にやってきた渡は、思わず息をのんだ。
捕獲用のゲージに、モコが入っているではないか?
「モコ! どうしたんだ?」
「ニャー……」
モコは、出してくれとばかりに鳴いた。どうやら、煮干しにつられて捕まったらしい。
「へへへ、つかまってくれたか。よしよし!」
不意に後ろから声がしたかと思うと、一人のおじいさんが立っていた。年は80代くらい、眼鏡をかけている。
「これ、あなたがやったんですか? モコを放してください!」
すると、おじいさんは不機嫌そうな顔で渡を見た。
「放す? とんでもない! ようやくわしがつかまえたものを。この猫はわしが飼うんだよ。利口でおとなしそうな猫だからねえ。ねずみとりにぴったりだ!」
渡はあまりのことにびっくりした。
「でもおじいさん、モコはこの森にすんでるんだよ。モコはここを離れたくないんだ!」
するとおじいさんは、渡がまるでひどいことでもいったかのように顔をしかめた。
「それがどうした? ここの森の鳥やネズミたちにとっちゃ、この猫がいないほうがいいんだ。どんどん増えて、あたりを荒らすんだから。それにこの野良だって、ちゃんとごはんがもらえる場所で暮らした方が、ずっと長生きできるってもんさ。なんかの拍子で死んでしまっては元も子もない」
そういわれると、渡は何と言い返せばいいのかわからなくなった。
「それとも、おまえが飼うっていうのかい? へへへへ、できないだろうねぇ! 飼えるんならもうとっくに飼ってるんだろうから」
「違う。僕とモコは友達なんだ! 飼いならしたいわけじゃない!」
すると、おじいさんは眉をひそめ、値踏みするように渡を見た。
「ふーん。じゃあなおのこと、モコに飼い主や住む場所があったほうがいいとは考えなかったのか? 素敵な飼い主がいたら、その飼い主がそのまま友達になってくれるだろう。そういう人を見つけようとは思わなかったのか? その方が幸せなんだって、わからないのか?」
矢継ぎ早にまくしたてられ、何も言い返せないまま、渡はじっとおじいさんを見た。
「ま、そういうわけだから、こいつはわしがもらっていくよ」
「待って! モコはあなたになついてないでしょ?」
すると、おじいさんは不敵な笑みをうかべた。
「だからどうした? たいていの野良は最初はそうさ。そのうちになつくようになる! 以前でっかいトカゲを飼ってたことだってあるんだ。昔このあたりに逃げてな」
おじいさんはモコのゲージを持った。モコは威嚇の表情で、シャーッとうなった。
「おっと! 凶暴な猫め!」
「やめて! モコをつれていかないで!」
渡はおじいさんの服をぎゅっと握ってにすがりついたが、おじいさんの表情はますます険しくなり、ものすごい力で渡の手を引きはがした。
「おまえが何をいっても無駄だ。もう決めたんだから!」
おじいさんは、渡をドン! と突き飛ばすと、振り返りもせず、さっさと歩きだした。渡はさっと立ち上がると、早足で追いながら話しかけた。
「待て! 待てよ!」
ところがおじいさんは、近くにとめてあった車にモコを押し込み、さっさとエンジンをかけて走り出してしまった! 渡は追いかけたが、もうどうしようもなかった。
モコが連去られた。あっという間の出来事だった。
呆然と立ち尽くすうちに、冷や汗が出てきた。
(どうしよう? どうしたらいい?)
考えても、気が動転して、いい考えはなにも浮かんでこなかった。
こんないきなりお別れだなんて……。広場を振り返ったが、そこには草がぼうぼうとはえているだけで、もうモコはいない。信じられなかった。
渡は茫然としたまま、家に帰った。ベッドの上に座って、さっきあったことを思い出していた。
(どうして話を聞いてくれなかったんだ? モコはあんなにいやがっていたのに。なんで一人で決めて連れ去ってしまえるんだ?)
思い出していると、あの時、ナンバープレートをとっさにメモしたり写真に撮れなかった自分が無性に悔しくなった。
それにしても、モコはいったいどこにいってしまったんだろうか?
こんなの、猫泥棒だ!
何か手立てはないだろうか? 何か……。
突然ふと、雪村まりんのことが頭によぎった。彼女は渡のほかに、唯一モコをかわいがってくれた、モコの友達だ。彼女に、モコが連れ去られたことを伝えなければならない。渡はそう思う反面、とても気が重かった。
とにかく、誰かと話さなければならない気がした。モコが連れていかれたのを止められなかったという事を……。
誰もいないリビングで受話器を握り締め、何度か電話番号を入れてみたが、通話ボタンを押そうとするたびに、気持ちが滅入って、押せなかった。
一時間ほどたってようやく、渡は電話をかけることができた。
「もしもし、時野戸くん?」
雪村さんの声は、どうしたわけか、少し緊張しているようだった。渡は、なるべく平静を保つのに必死だった。
「……この番号、時野戸君だよね? どうしたの?」
「あの……」
「なに? なんか変だよ?」
「……いわなきゃいけないことがあって」
「どうしたの?」
「……。モコが……連れていかれた」
「えっ?」
「……」
渡は、ぎゅっとこぶしをにぎりしめた。
「どういうこと? モコが連れていかれたって……」
もうそれ以上、言葉につまってしゃべれなくなった。冷たい沈黙が横たわった。
「——ねえ、時野戸くん、2時頃あの広場に来れる? 話聞かせて。私、そっちいくから」
渡は驚いて、思わず顔をあげた。
「でも……」
「大丈夫、夜までには帰れるわ。必ず行くから。ね、待ってて。お願い!」
「……わかった」
「お願い、きっとね」
雪村さんはそれだけいうと、通話を切ってしまった。
渡はベッドの上で、しばらくぼーっと座っていた。雪村さんに会えることは嬉しいことのはずだったが、今の渡には気が重かった。
2時前、彼女が引っ越した後に撮ったモコの写真を何枚か選ぶと、渡は広場に向かった。
「モコ! モコ!」
広場に来て、渡は最後の願いとともに呼びかけた。だが、やはりモコが現れることはなかった。ベンチに座り込むと、モコの写真を引っ張り出してみていた。
(モコ……)
涙が、ポタッと写真の上に落ちた。
「時野戸くん……」
ふと顔をあげると、雪村さんがやってきていた。渡は慌てて涙をぬぐった。
「モコが連れていかれたって……」
渡は、黙ってうなずいた。
「いったい何があったの?」
雪村さんは、不安げな顔で渡を見ていた。渡は、最近モコがおびえていたこと、数日前、家に泊めたこと、翌日広場に返したこと、それから、ついさっきおじいさんがモコを捕まえて、問答無用で連れて行ってしまったことを話した。雪村さんは真剣な表情で渡の話を聞いていたが、とうとう怒り出した。
「そんなのおかしいわ! 事情はどうあれ、問答無用で急に連れて行くなんて!」
「僕もそう思う。でも、止めても聞かなかったんだ。こんなのあんまりだ!」
「ええ」
雪村さんは、悲しそうなまなざしで渡を見た。
「じゃあ、モコはそのおじいさんが飼うことになったのね……」
「たぶん……。だけど……モコ、大丈夫だろうか? 住所を聞くひまさえなかったんだ」
雪村さんは考え込んだ。
「またここにくるかしら」
「どうかな。モコを連れて行った以上、もうここには用がないだろうし……」
「……そうね」
「これ……。モコの写真」
雪村さんは写真を見つめたまま、言葉を探しているようだったが、どこにも見つからないようだった。だが、しばらくしてから、口を開いた。
「ねえ、時野戸くん。あなたのせいじゃないわよ。モコはあなたのことが大好きだった。あなたが、モコを大好きだったように。あなたはモコの一番の友達だったんだから……」
「でも……止められなかった」
ついに耐えきれなくなって、渡は泣き出してしまった。恥ずかしい気持ちでいっぱいだった。でも、どうしようもなかった。
「いつまでも、一緒にいられると思ってた! もっとずっと、一緒にいられると思ってたのに!」
雪村さんは泣き出して、頭を寄せ、肩を優しく抱きしめた。
「ごめんね。私、何もできなくて……」
謝ってほしいだなんて、渡は全然思っていなかった。友達を失ってしまった悲しさで、それ以上何も言えないまま、渡はぎゅっと雪村さんの腕をつかんだ。
雪村さんの涙が、ぽとんと写真に落ちた。