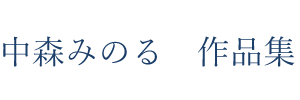2章 2
告白の日がやってきた。
その日は「水色」というテーマで、商店街の中を撮っていた。サークル中ずっと気が気でなく、渡はぼやけた写真を何枚も撮ってしまった。幸い、みんなは自分の写真をうまく撮るのに夢中だった……と、雪村さんが、レンズをこちらに向けていた。
パシャッ。
シャッターが切られ、慌てた渡の顔がフィルムに焼きついた。雪村さんは真剣なまなざしをゆるめ、にこっと笑った。
「すきあり!」
渡もつられて笑うと、パシャッと雪村さんを撮り返した。こういうじゃれあいは、サークル内でよくあるお遊びだった。少しだけ、緊張がほぐれた気がした。
サークルが終わると、みんなは現場で解散した。渡と雪村さんは、同じ電車にのって、夜景がきれいに見えるスポットに着いた。駅から階段を上っていくと、眼下に街並みが広がっていて、まだ夕日が輝いていた。
「わぁー!」
雪村さんが、さっそく夕日を写し始めた。渡はベンチに座ると、ぼんやりとその様子を見つめた。夏の夕暮れの気配が漂っていた。
「おなかすかない? 食べ物買ってくるよ。飲み物は紅茶でよかった?」
「ありがと。うん、冷たいミルクティがいい」
「わかった」
渡は、事前に調べておいた、おいしいと噂のホットドッグを2つ、それと、自販機で紅茶とコーヒーを買った。雪村さんはベンチに座って、景色をじっと眺めていた。と、その時街灯がつき始めた。あたりは薄暗くなってきている。
「はい」
雪村さんは渡に気がつくと、ホットドッグを受けとった。たっぷり卵がはさんであって、ケチャップとマスタードがかかっている。
「わぁー、おいしそう! おなかぺこぺこ!」
雪村さんはホットドッグにかぶりつくと、今度は急いでミルクティを飲んだ。
「そんなに急がなくても大丈夫だよ」
渡が笑うと、雪村さんは恥ずかしそうにした。
「だって……! おなかへってたんだもん」
「ごめんごめん」
渡もホットドッグを食べ始めた。ところがしばらくすると、また緊張がぶり返してきた。
(ふられたらどうしよう……)
渡は不安を紛らわすように、ホットドッグを食べた。あたりはさらに暗くなってきて、街の明かりもついてくると、だんだん夜景らしくなってきた。二人は立ち上がり、フェンスに近寄った。
「きれいね」
「ほんと」
「撮る?」
「うん」
渡と雪村さんは、夜景の写真を何枚か撮った。大都市のようなきらびやかさはなかったが、静かな温もりを、その景色から感じ取っていた。そのせいか、数枚とっただけなのに、不思議と胸がいっぱいになってしまった。
渡は、カメラをおろすと、夜の空気を吸い込んだ。
「撮らないの?」
雪村さんが、こちらを向いた。
「うん」
「それじゃ、私も休憩」
二人はしばらく夜景を眺めていた。他愛もないおしゃべりを、もうずいぶんしてきたけど、こういう時に限って、何を話せばいいかわからなくなってしまう。一方雪村さんは、沈黙も気にしていないようだ。渡は、また緊張し始めないうちに、告白することにした。
「雪村さん」
「なに?」
雪村さんがこっちを向いた。ケチャップがほっぺたについてる。
「言いたいことがあって……」
「——うん」
普段はにぶい雪村さんも、とうとう何かを感じ取ったらしく、緊張した面持ちで渡の方をしっかりみた。
「中学生の頃から、ずっと好きでした。つきあってください」
「……はい」
時間が、止まっていた。とうとうこの時が来たんだ。
「よかった! とっても嬉しい」
「私のほうこそ……ずっと時野戸君のこと、好きだった」
「えっ? ほんと?」
「ええ。ずっと前から」
「ほんとに? それっていつから?」
「——それは内緒。時野戸君は、いつから?」
「僕は、動物園に行った時の帰り……かな。好きなんだって気づいたのはもう少し後だけど。ほんとは引っ越す時に言いたかったんだけど……言えなかった」
「どうして?」
「関係が壊れるのが怖かったんだ。でも、モコがいなくなった時……抱きしめてくれて、本当にうれしかった」
「そんなこと……恋心がなくても、だきしめたわ」
「そっか……。うん」
渡はようやく、雪村さんが愛してくれていたことに気がついた。すると、どうしたわけだか、涙が出てきた。さっとうつむくと、ポケットティッシュを取り出してふいた。それからティッシュを、雪村さんに渡した。雪村さんは不思議そうに受け取った。
「なに?」
「ケチャップついてるよ。ほっぺた」
渡がそういうと、雪村さんの顔が、みるみる赤くなった。
「うそっ! はやく言ってよ! 台無しじゃない!」
雪村さんは、急いでケチャップをふき取った。
「台無しじゃないよ、それくらい」
飛び出した言葉に、渡は自分で照れてしまった。渡は、慌てて写真を出すと、パシャッと撮った。
「すきあり!」
「……もう!」
まるで雪玉のようなティッシュが、ポーンと飛んできた。
それからの日々は、渡の今までの人生の中で最も輝かしい季節だった。サークルでも二人で活動することが増えたし、それとは別にデートに出かけた。サークルのない日はアルバイトをして、デート代やサークルでの旅行費をためたが、ただでさえ忙しい日々でお金に余裕はなかった。少ない中でやりくりしながら、二人はたくさん楽しい思い出を作った。
行きたい場所は山のようにあったので、二人で計画を練ってたくさん出かけた。時々取るに足らないことで喧嘩もしたが、だいたいいつも、どちらからともなく謝り仲直りした。仲直りした後は決まって、お互いの写真を撮りあった。
撮影会と探検旅行を兼ねたサークル旅では、海に行ったり、秋になると紅葉を撮りに行ったりと、とても楽しいものだった。全年生で参加するものや、同じ学年だけで行うものなど、1年に4回ほどあって、その旅で写真コンテストにも出す写真を撮ったりと、充実していた。
クリスマスは、サークルのメンバーでパーティをした。
そのころには、それぞれの呼び方も決まっていた。池沢 翔太はショー、小松浦 穂乃花はほのか、間鳴梶朗はカゲロウ、島田 真菜はまなちゃん、南木谷 十九はジューク、時野戸 渡はわたる、藤未りおはりお、雪村 まりんは、まりん。
年越しと正月、渡とまりんは一緒にすごした。
2月。残念なことに、池沢翔太はサークルをやめた。軽音サークルと掛け持ちしていて、そっちに熱中したことが原因だった。ところが、辞めた後も時々顔を出すので、メンバーは彼がやめた気がしなかった。
生物の環境に関する授業も面白かった。渡と雪村さんは、臆面もなく一緒の授業を受けていたが、学部が違うためサークルのメンバーとかぶる授業はまずなかったので、平気だった。
2年生になると、サークルの伝統で、メンバーにボールペンが配られた。ボールペンには、ポルロイド・ストロールの文字が印字されていた。ロゴ風でおしゃれだ。
毎年サークルの3年生が2年生に記念の品とを送っているそうで、今年の3年生の場合はおそろいのTシャツ、4年生はキーホルダー、卒業した先輩の時は写真立てということらしい。
春が来ると、渡と雪村さんは、河川敷の桜を撮りに出かけた。撮影のために出かけているのか、それともデートのついでに写真を撮っているのか、もう二人ともわからなくなっていた。
渡とまりんは、とてもいい状態で交際を続けていた。ところが、初夏も過ぎ、夏の初めになると、雪村さんは、どうもうかない表情を浮かべていることが多くなってきた。わけを聞いても教えてくれない。
(なんだかまずい気がする……)
渡がそう思っていた矢先、雪村まりんから話を切り出された。
なんと、イギリスの大学に編入する、だからもう別れてほしい、という話だった。あまりに思いがけないことに、渡は戸惑った。卒業するまで待つという渡に対して、雪村さんは頑なに拒んだ。理由を聞くと、まりんはこう答えた。
「あのね……私は、渡の機会を奪いたくないの。編入するんだから、日本に帰ってくるかもわからないのよ?」
「どうして教えてくれなかったの?」
「言い出せなかった。どうしても。だって、別れてしまうことになるもの」
「でも、そんなの……。つらいよ」
渡は、はっとまりんを見た。まりんの目から、涙が流れていた。
「私だって……! 私だって、とってもつらいわ! でも、こうするしかないの!」
雪村さんの表情は硬く蒼白で、唇がかすかに震えていた。もうずいぶん悩んだ後の結論だと、渡はようやく気づいた。
つまり、渡が何を言ってももう無駄だったのだ。
「——いつ、イギリスに行くの?」
「9月2日よ」
「あと1か月とちょっと……か。それまでは一緒にいられるの?」
だが、驚くべきことに、雪村まりんは首を横に振った。
「一緒にいる時間が長ければ長いほど、離れがたくなるわ」
認めたくなかったが、雪村さんの言う通りだった。堪えがたいほどの苦しみが、渡の心を襲っていた。
「……わかった」
渡はふられた。こうして二人はあっけなく別れた。
その日から、渡の生活は、色を失ってしまったかのように、くすんで見えた。世界は灰色で、乾いたもののように感じられた。
雪村まりんの態度は、あたりさわりのないものとなった。だが、いままで親密だった分、そっけなく思えて、渡には耐えがたかった。
こういうわけで、サークルでの活動は、なかなかつらいものになった。だが、8月末の、夏の旅行が残っている。よりを戻せるとは考えていなかった。だけど、その時くらいはせめて、彼女と最後の思い出ができるんじゃないかと、渡はひそかに期待していた。
渡は、お別れの品と、旅行のお金を貯めるために、アルバイトを一生懸命やった。引っ越しのアルバイト、工事現場でのアルバイトなど……どれもきつかったが、働いて体を動かしている間は何も考えずに済んだのがありがたかった。
そうこうしているうちに、サークル旅行まであと2日となった。
8月17日。全員がばらばらに活動するという、めずらしい日だった。
池沢はいつものように見知らぬ人物を撮りに行き、小松浦さんは川や橋からみた景色を、間鳴は森に虫を撮りに行き、島田さんはあいにく病欠、南木谷はお寺や神社に、藤未さんは新しくできたスイーツのお店、雪村さんはアンティークショップへ向かうらしかった。
渡は、撮影候補ボックスからくじを引くことにした。これは、サークルが考案した、撮影スポットのくじ箱で、いい撮影スポットを見つけたら、誰でもこの中にいれていいという箱だった。撮りたい場所が決まらない時に使うもので、渡は久しぶりにこの箱を使うことにした。
「木途隠町……?」
くじで引いたのは知らない町だった。一瞬ためらったものの、こういう時こそ知らない街の方がおもしろいかもしれないと思いなおした。渡は場所を調べると、電車に乗り込んだ。
街の中心街は人でにぎわっていた。店がいくつもあり、多くの人が行き来している。ところが、少し中心からそれると、すぐに人通りがなくなった。渡は、通りの写真を何枚か撮ったり、その近くの橋の写真を撮ったり、だれもいない公園の風景を撮ったりした。そうこうしているうちに日が落ちてきたので、渡は夕日と一緒に撮れそうな場所を探した。すると、遠くの方にビルが2つ、ニョキッと突き出ているのが見えた。
(夕日をバックに、ビルを撮ってみるのもおもしろいかもしれない)
渡は、ビルに向かってふらふらと歩き出した。ところが、思ったよりもずっと遠かったのか、なかなかたどり着かない。ようやくたどり着いたころには、夕日はもう沈みかけていた。
ビルの正面に来た。思ったよりも小さい。渡は、道を挟んでビルのちょうど向かいから急いで何枚か撮った。ビルの近くには、通ってみると面白そうな路地裏があり、もう少し先には商店街があったが、渡はもうこれ以上動く気にはなれなかった。渡は歩道に備え付けられたベンチに腰を下ろし、汗をぬぐった。苦労したけど、いい写真が撮れた。
渡は、どっと疲れが出たのか、いつの間にかそのベンチで眠りこけてしまった。
妙な夢を見た。白いガードレールに、白いおおきなシールが張り付いている。誰もそのことに気がつかない。自分だけが偶然気づく。気になってはがしてみると、謎の場所と時間が書かれている。好奇心にあらがえず、その場所へ行くと……。
妙な感覚に陥って目を覚ますと、あたりは暗く、もうすっかり夜だった。時計を見ると、夜の8時2分だ。渡は慌てた。もう帰らないといけない。急いでカバンを背負うと、近くに駅がないか探し始めた。
道を確認するために顔をあげ、ふとビルの方を見ると、その隙間から星が見えた。
(あんな隙間、あったかな?)
星がチカチカッと瞬いている。
不思議に思い、ビルの隙間を、地面に向かって目線をずらしていくと、なんと、ビルとビルの間に小さな建物があるではないか? 建物には正面に看板が掲げてあり、【占い】と書いてある。
(ビルの間に、占い? あんなのあったっけ?)
渡は占いを信じていない。それなのに、その時はどういうわけか、頭にもやがかかったように、その占いの建物が無性に気になってきた。人通りもなく、あたりはしんと静まり返っている。
渡は、もう帰らないといけないという事も忘れ、ついふらふらとガードレールをまたぐと、道路を横切り、占いの建物の前まで来てしまった。
中は暗く、どうなっているのかわからなかった。のぞいてみると、階段が下へ下へと続いている。灯りは所々ついていた。目を凝らして先をてみると、そのあまりの深さにギョッとした。
底知れず。まるで死の国まで続いているような気がした。
好奇心がうずいた。だけどもう、帰ったほうがいい。そう思うのに、どうしたわけか、下に降りていきたいという欲求が抑えられなくなった。まるでなにかに魅せられたように、また階段の先をのぞき込んだ。この先に、占い師がいるんだろうか?
自分でも思いがけず、突然、、足が一歩階段を踏みおりた。不思議なことに、一歩踏み出してしまうと、急に抵抗がなくなった感じがした。吸い込まれるような浮遊感と共に、体が勝手にずんずんと下へ向かう。
階段はまっすぐ続いていた。30段ほど下りてもまだまだ続いている。地下2階なんてものではない。
普段なら、こんなおどろおどろしい所はごめんだった。それなのに、渡の頭はもやがかかったかのようにひどくぼんやりしていて、恐ろしさはほとんど感じなかった。
5分……10分……。
一体どれくらいの時間がたっただろうか。渡はいまやもう夢中で一本道の階段を下り続けていた。地下こんな深い場所で、占いなんてやっているんだろうか?
ところがとうとう、曲がり角に出くわした。踊り場が現れたのだ。踊り場から、階段は右へ曲がっていた。それが最初で最後の曲がり角、そこから5段あった階段を下りると、とうとうつきあたりに占いの部屋が見えた。
(ついた……)
古めかしく、重そうな木の扉だ。扉の上には、金属で作られた目のレリーフが飾られている。
目のレリーフには太い4本のまつげがあって、はるか先を見つめていた。その扉を、ぼんやりとした灯りが照らし出していた。ここで間違いない。
渡は、ドアノブに手をかけようとして、少し迷った。なんだか不安な気持ちだった。
だけど、ここまできておいて、いまさら帰る気にもなれない……。
ガン、ガン、ガン、とノックをした後、思い切ってノブをまわすと、グッと引っ張った。扉はギイィッときしんで開いた。
渡は、さっと体を滑り込ませるようにして入った。
バタン!
ドアが大きな音を立てて閉まった。
その瞬間、動かないはずのレリーフの目玉が、ギョロッと下を向いた。