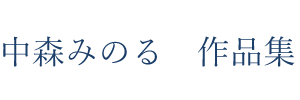2
時野戸渡は中学2年の男の子だ。背はクラスで中くらい。髪の毛はストレートだったが、くせがつきやすく、いつもどこかはねていた。
渡には秘密があった。
家から山に向かって歩いていくと、誰もいない林道に出る。その道の途中に、草に覆われた小さな広場があった。
「モコ! モコ!」
広場の屋根つきベンチの座面に、一匹の野良猫がぴょこんと飛び乗った。八割れ模様の灰色と白の柄の猫で、足は白い靴下をはいているみたいだ。
この猫こそが、渡の秘密だった。
渡がモコと出会ったのは子猫の時だ。小学校6年生の秋の昼下がり、鳥の観察に出かけた散歩の途中のこと、歩き疲れ広場のベンチで寝ていると、何かがおなかによじのぼってくるような感触があった。みると、小さな猫がお腹の上に乗っていた。子猫は逃げ様子もなく、渡をみつめている。
なんてかわいい猫だろう!
頭をなでると、子猫は嬉しそうにごろごろいった。どうも親離れしたばかりらしい。モコは、渡を気に入ったらしく、じゃれついた。渡は子猫と友達になった。毛がもこもこしていたので、モコと名づけた。
それからというもの、渡は毎日のようにこの広場に来て、モコと一緒に遊ぶようになった。
モコはとても賢く、気性もおだやかな猫だった。モコはあまえんぼで、いつも膝の上に乗りたがった。渡は学校が始まる前の朝早くにモコに会いにいったり、放課後に一緒に遊んだ。
モコがひざの上にいる時、渡は学校での出来事や悩みを話した。嫌なことがあったら、モコはだまってその話を聞いてくれたし、おもしろいことがあった時には、興味深そうに渡の顔を見たりした。
こうして何年も一緒に過ごすうちに、モコは渡の大事な友達になった。できればモコを家で飼いたかったが、家族はアレルギーがひどく、飼うことはできなかった。それに、モコはこの小さな広場と、その奥の森をとても気に入っていて、渡がどこかへ連れて歩こうとすると、とたんに嫌がるのだった。
そこで渡は、お小遣いをためて買ったペットハウスをこっそり木の下に作った。毛布を中に敷くと、モコはずいぶん気に入ってくれた。
秋が来て、冬が来て、中学三年生になっても、モコは変わらず広場の近くの森の中にいて、渡が会いに来るといつもひざに乗ってきた。
ところがそんなある日、渡の秘密が暴かれてしまったのだった。
始業式が終わって一週間ほどたった。その日渡はモコと遊んでから登校した。すると、教室に入るなり、クラスメイトの雪村まりんとばったり出くわした。するとまりんはどうしたわけか、渡をじろじろと見てきた。
「なに?」
渡はあわてて上着を脱ごうとしたが、それより先に、まりんは渡の服についていたモコの毛をつまみとった。
「ねえ、これって猫の毛よね? 時野戸くん、猫飼ってるの?」
「え? いや……」
「私、わかるんだ。ねえ、猫飼ってるんでしょ?」
「ちがうよ。風で飛んできたんじゃない?」
すると、まりんはくすっと笑った。
「うそ! だって、いっぱいついてるよ」
渡は自分の制服を見て、しまったと思った。たしかに毛がたくさんついている。
「——別に。雪村さんには関係ないだろ」
雪村さんは不機嫌そうな顔になったが、すぐに笑顔を取りつくろった。
「まーね。私には関係ないわよね」
その時、石丸先生が教室に入ってきた。渡は急いで自分の席に戻った。授業が始まると、モコの秘密がばれなかったことに、渡はほっとしていた。
そのせいだろうか? 雪村さんが授業中ちらちらと様子をうかがっていることに、渡は気がつかなかったのだった。
放課後になると、渡はいつものようにモコに会いに行った。ところが、何ということだろう! 電柱に隠れながら雪村さんがついてきているではないか? それなのに、渡はちっとも気がつかないまま、広場へ到着してしまったのだった。
「モコ! モコ!」
モコがぴょこっと顔を出した。そのとたんモコは、渡の後ろにいた雪村まりんを見つけ、ビクッと草むらに逃げ込んだ。
「どうした? モコ!」
「へぇー! やっぱり猫と遊んでたんじゃない」
びっくりして振り返ると、雪村さんが、いたずらっぽく笑っていた。
「雪村さん!」
「ふふ、ついてきちゃった! ごめんね」
「なんでつけてきたんだよ」
「だって……気になっちゃって」
渡はいらいらした。だが、見つかってしまった以上どうしようもない。
「あの猫、子猫の頃から友達なんだ。モコっていうの。——モコ!」
モコは茂みの中でじっとしたまま、近づいてこない。警戒させてしまったらしい。
「あーあ、今日は無理かな。……雪村さん、このことは秘密にしといてよ」
「なんで?」
「だって、いろんな人が知ったらやっかいだよ。モコが人気でちゃったら、一緒に遊ぶ時間も減っちゃうしさ」
「そっか。わかった」
「絶対だよ?」
「うん。二人だけの秘密ね」
渡はあやしむように雪村さんの顔を見た。いつもはぼんやりとした表情が、この時ばかりは真剣そうな顔だったので、少しは信用していい気がした。
「私もモコと友達になりたいな」
雪村さんは遠慮がちにいった。
「そりゃ、僕は別に構わないけど……モコ次第かな。モコが慣れないことにはどうしようもないから」
「そうよね。ねえ、どうやったらなつくの?」
「どうかな。おどかさないようにして、すこしずつ近寄るってことかなあ。まあ、ちょっと離れて見ててよ」
雪村さんは後ろへ下がった。ゆっくりモコに近づいていくと、モコは警戒しつつも逃げなかった。渡はモコを抱き上げると、ベンチの上に座った。
「雪村さんはそこでじっとしてて」
いきなり距離をつめるのはよくない。モコをいつものようになでると、雪村さんはそれをうらやましそうに見ていた。しばらく時間がたったころ、モコは渡の膝から降りて、雪村さんのほうをじっとみた。ところが、それもつかのま、そそくさと森の中へ入っていってしまった。
「今日はここまでかな。仲良くなるのにどのくらい時間がかかるかわからないけど……どうする? また見に来る?」
すると雪村さんはにこっと笑った。
「また来たい! 明日も!」
渡は、少しドキッとした。でも、そんなこと、気づかれたくない。渡はなんでもない顔をして、雪村さんを見た。
「ふーん。じゃ、明日もここに来よう。だけど、部活はどうする?」
「私、写真部なんだ。ゆるい部だから自由に行動していいの。時野戸くんはバスケ部だっけ?」
「そうだけど、僕も半分幽霊部員みたいなもんだし……。補欠なんだ」
「補欠……ね。じゃ、明日の放課後でいい?」
「うん。日直で少し遅れるかもしれないけど、先に来ててもいいよ。なつくまでは、僕が呼ばないと出てこないかもしれないけど」
「わかったわ」
話しながら帰っているうちに、分かれ道に来た。
「私、こっちだから……じゃあ、また明日」
「うん」
渡は、雪村さんの後ろ姿をしばらく見送った後、また歩き出した。
雪村まりん。天然パーマで、度がきつそうな眼鏡をかけている。
目が少しはれぼったいせいか、いつも眠そうに見える。それどころか、ほんとにぼんやりしていて、上の空のことが多い。成績がいいという噂も聞いたことがない。背は中くらいで、すらりとしている。ひかえめな性格のせいか目立つことはなく、いつも友達にひっつくように立っていた。
渡は、彼女が写真部であることは知っていた。部活中、体育館の窓から彼女が写真をとっているところを見たことがあったからだ。とはいえ、同じクラスになったのは初めてのことで、いったいどんな人なのか、まだわからなかった。だけど、モコのことを言いふらすような人には見えなかったので、不思議とその点は安心していた。
「あ! 来た来た!」
次の日、部活をさぼって広場にいってみると、雪村まりんはもう広場の入り口で渡のことを待っていた。手にはカメラを持っている。
「ごめん、待った?」
「ううん、本読んでたから。それより、早く呼んでみて」
「わかった。——モコ! モコ!」
向こうの茂みががさがさいった。にゃーんという鳴き声が聞こえたかと思うと、モコが姿を現した。モコは遠くの雪村さんをじっと見ていた。
「そうそう、煮干し持ってきたんだ。ほんとは餌やりはいけないんだけど、最初の2、3日だけ。ちょっと持っといて」
煮干しが入った袋を雪村さんに手渡した。モコに餌をあげることは滅多になかった。けれど、モコがお母さんになって子猫を見せてくれた時、煮干しを少しあげたのだが、モコはこれが大好きなのだ。渡はいつものようにモコを抱き上げると、膝の上にのせた。
「それじゃ、最初は僕に渡してくれる?」
「わかったわ」
渡が受け取った煮干しをもぐもぐ食べるふりをすると、モコは顔を近づけて欲しがった。そこで煮干しをあげると、モコはムシャムシャと食べ始めた。
2、3回そんなやりとりがあった後、ついに雪村さんが、自分の手から煮干しをあげることにした。モコは、ふんふんと手のにおいをかいでから、煮干しを食べた。二人とも嬉しくなって、思わず顔を見合わせて笑った。
「うまくいったね。これを続けていけば、そのうちなつくと思うよ」
「良かった! そのうち写真も撮れるようになるかな?」
「モコが嫌がらなければね。カメラを見慣れてないから、最初はびっくりしちゃうかも」
「うん。もうちょっとなついてからにする」
モコは煮干しを食べながら、何を話しているんだろうと二人の顔を見ていたが、昨日ほどの緊張はないようだった。この調子だとうまくいきそうだ。
それから毎日、渡と雪村さんは広場を訪れて、モコといっしょにあそんだ。煮干しをあげたのは最初の3日だけで、そのあとはねこじゃらしに変わった。一週間ほどたったころ、モコはとうとう雪村さんになでさせてあげることにしたらしく、自ら膝の上に乘ってきた。
「ああ、ついに!」
雪村さんが、そーっと背中をなでると、モコは気持ちよさそうに目を細めた。モコはじっとしていたが、そのうち雪村さんの足はしびれてきたらしかった。幸福と苦痛が同時に訪れることがあるのを、彼女はこの時初めて知ったようだった。
「ねえ、時野戸くん、モコを抱っこして!」
「うん」
モコを抱っこすると、雪村さんはすかさずふとももをさすった。
「ひゃ~、しびれちゃった!」
渡はその様子が面白くって、思わず笑った。雪村さんは、さするのに夢中のあまり、思わず前につんのめってこけそうになった。
「おっと!」
渡は手をつかんで雪村さんを支えると、雪村さんは恥ずかしそうに笑った。
「慣れててもしびれるからね。こればっかりはどうしようもないよ」
「うん。……ねえ、今なら写真も撮れそうな気がする。そこに立っていてくれる?」
「最初はカメラを向けずに、風景を撮っといた方がいいかも」
「そっか」
雪村さんは広場の端っこまでいって、持ってきていたポルロイドカメラを取り出した。モコは不思議そうな顔で、それを見ていた。雪村さんは最初、渡の言った通り、風景をとるふりをして、時々モコの近くにもカメラを向けた。モコは別に驚くわけでもなく、その様子を見ていた。雪村さんは、また違う方向にカメラを向けた後、さっとモコに向けると、ほんの少しの時間でシャッターを切った。早撃ちならぬ、早撮りだった。
「やった! 撮れた!」
雪村さんは、カメラをかばんの中にしまうと、嬉しそうに近寄ってきた。しばらく待ってから現像された写真を見ると、渡とモコがちゃんとうつっていた。
「すごい! でも、ちょっと恥ずかしいな」
すると、雪村さんはいたずらっぽく笑った。
「ふふ、あげる」
「いいの?」
「うん。これからまだまだ撮るもん」
「じゃ、もらっとく。 ほら、モコ! お前がうつってるよ」
ところがモコはペロッと写真をなめようとしたので、渡は慌てて腕をひっこめた。渡は改めて写真を見た。どこか懐かしいような、そんな写真だ。
「へー、やっぱり上手なんだね」
「そう? ありがと」
雪村まりんはまんざらでもない顔をした。
その日以降も、予定のない日は放課後モコのいる広場に二人で来ることが恒例になり、雪村さんはモコの写真を何枚も撮った。モコもすっかり慣れてきて、どうぞご自由に、といわんばかりに、ひざにのってくつろいでいた。
雪村さんはいつもはぼさっとしているのに、シャッターを切るときは真剣なまなざしになることに、渡は気づいた。惹きこまれるような、そんな姿勢だった。
「ねえ、時野戸くんも写真撮ってみない? おもしろいよ」
ベンチに寝転びながら空の写真をとっていた雪村さんが、ふと渡を見ていった。
「撮り方とかわかんないし……」
「別に難しくないわよ。シャッターを切れば撮れるんだから」
「まあそうだろうけど。構図とかいろいろあるんでしょ? 詳しいことは知らないし……」
「じゃ、教えてあげる」
よほど写真が好きなのか、雪村さんは熱心に教えてくれた。渡は写真について教えられたまま、ひとまずポルロイドカメラで何枚か撮ってみることにした。
モコ、それから花、雲、森……。時間と空間を閉じ込めたかのように印画紙に浮かび上がってくるのをみていると、渡はなんだかドキドキした。
「ね、おもしろいでしょ?」
「うん」
「カメラ持ってる? どんなカメラでいいわ」
そういえば、家に使っていないカメラが置いてあったのを、渡は思い出した。高いカメラじゃないけど、充分に使えるものだったはずだ。
「デジカメと、あと古いフィルムカメラがあると思う」
「デジカメがいいと思うわ。最初はそっちの方が簡単だから。それじゃ、今度一緒に撮りに行かない? 何か撮りたいものとかある?」
「うーん……雪村さんは?」
「私は風景とか動物とか、道で見つけた花とか、なんでも」
「その中じゃ動物がいいかも。面白そうだし、動物も好きだし……それじゃ、動物園に行ってみる?」
「いいわね。 次の土曜日はどう?」
「あいてる」
「やった! それじゃ動物園の入り口に、十時集合にしよっか」
「わかった」
会話の流れで、二人はいつの間にか一緒に動物園にいくことになった。雪村さんと別れ、家につくと、渡は大急ぎでカメラを探した。
充電式のデジタルカメラはすぐに見つかった。電源を押すとすぐに起動した。確かにこっちのほうが簡単そうだ。渡は、充電をしながら、撮りたい写真を思い描いていた。
土曜日がやってきた。動物園の最寄り駅についた時、私服で会うのも初めてなら、女の子と外で一緒に遊ぶのも初めてのことだということに突然気がついた。
(もしかして、これってデート?)
渡はそわそわしだした。
待ち合わせ時間の3分前に、雪村さんがやってきた。私服は野暮ったかったが、不思議と似合っている。一緒に写真を撮りに行けるのがうれしくて、うきうきしてきた。
「おはよ。待った?」
「全然。今着いたとこ」
「デジタルカメラだっけ? 見せて」
「うん」
首にかけていたカメラを雪村さんに渡すと、彼女はじっくりとカメラを調べる。
「いいカメラね。味があるわ」
「そうだね」
「デジタルカメラは操作がそんなに難しくないから、使いやすいわよね。フラッシュはたかないように設定して……と。たくさん撮ってもフィルムが減っていかないのは、気楽でいいわ。今日はいっぱい撮っちゃお。私の真似してとってみてね」
動物園に入ってすぐ、カメラの撮り方のレクチャーをうけた。そこまで難しい感じでもない。この模木芽動物園は撮影可能だ。
フラッシュがオフになっていることを確認すると、二人はさっそく写真を撮り始めた。構図を教わりながら、雪村さんと肩を並べて撮っているうちに、渡はなんだか妙な一体感を感じて、そわそわした気持ちになった。
それにしても、なんてたくさんの動物がいるんだろう。
動物園は何度も来ていたが、そのたびにいつも新しい発見がある。悠々としたライオンの姿も好きだし、別世界に来たような気分になれるフラミンゴも素敵だ。普段なら決して見れないような生き物たちが、この地球のどこかで暮らしているという事実が、渡の胸を高鳴らせた。二人は満足いくまでシャッターを切り続け、気がつけばもう3時間ほども経っていた。途中持ってきていたお茶がなくなったので、渡はグレープジュースを、雪村さんはミルクティを買うと、ベンチで飲んだ。
「結構撮れたわね。もう一度見せて」
雪村さんが何度目か、顔を近づけて渡のデジカメを確認した。
「いいわね」
「うん」
二人とも、たくさん写真を撮れたことに満足した。そこで二人は、単に動物園の中をぶらつくことにした。
「こんなに楽しいなんて思わなかった。また一緒にどこか撮りに行きたいな」
渡は思ったことをつい口走っていた。雪村さんが、パッと明るい笑顔になった。
「いいわね! 時野戸くん、写真向いてるんだと思う!」
「そうかな」
「きっとそうよ。ね、じゃあ今度はどこ行く?」
「うーん……散歩しながら撮るのも面白そうだな」
「いいわね。私よくやるわよ。それじゃ今度は、一緒に散歩しよっか」
「うん、そうしよう」
二人はそれから、時々写真を撮りに出かけるようになった。近くの海に行ったり、商店街の中を撮ってみたり、自然公園の中を歩きながら撮ったり。二人はとても仲のいい友達になった。
けれど、突然お別れすることが分かった。雪村さんが、引っ越しすることになったのだ。北の隔深市という知らない土地で、電車で5時間もかかるようなところらしい。
渡にとって、とてもつらいことだった。雪村さんの気持ちはわからないが、渡はいまやもう、彼女に対して友達以上の気持ちを抱いていたからだった。
けれども、親の都合らしく、どうしようもなかった。最後に、思いを伝えようか……と思ったが、できなかった。
二人の楽しい思い出が、壊れてしまうのが怖かったからだった。
二人は、最後の日が来るまで、明るく過ごした。終わりなんて来ないかのように。
だが、終わりはやってきた。
雪村さんは広場でモコと渡にお別れを告げると、引っ越していってしまったのだった。
ところが、その一ヶ月後、事件は起こった。