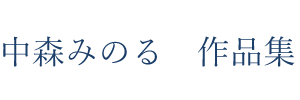「雨、やみまシータか……」
雨雲から、最後の一粒が落ちた。雨粒はケロール博士のほっぺたに落ちると、まるで泣いているように、頬を伝った。その雨粒が地面に落ちると同時に、ケロール博士は変身を始めた。
カエルの顔が次第に小さくなって、膜から耳が突き出た。
背はぐんぐんと伸びていく。
頭の上から黒々とした髪の毛がニュッと生えてきて、あいていただけの鼻の穴は、次第に固く小さな鼻になっていった。肌は緑から黄色っぽい色になり、やがて肌色になった。目玉はしだいに近づいていって、眉も次第に濃くなってきた。
変身が終わると、そこにはびしょ濡れの男がたっているばかりで、もはやカエル人間のおもかげはどこにもなかった。
「うわ~っ!」
渡が思わず叫ぶと、ケロール博士はキョロッと渡の方を見た。
「きみ、だれ?」
ルーキオがあわてて渡の手を引っ張った。
「おい、いこうぜ」
「うん」
渡たちはそそくさとその場を離れると、近くの路地裏に入った。そのとたん、向こうから雲のようにふわふわ浮いた羊に乗った青年がやってきた。
「博士、いったいどこにいっちゃったんだ?」
青年のほっぺたには、べったりキスマークがついていた。
「おい」
見かねたルーキオが、笑い出したいのをこらえながら、青年を呼び止めた。ルーキオが自分のほっぺたを指さすと、青年はキスマークに気づいた。
「……ルナのやつ!」
青年はあわてて頬をごしごしとこすった。
「博士ならここを出た通りにいたぜ」
「ほんとですか? ありがとう!」
雲のような羊に乗った青年は、そのままふわふわ路地裏を飛んでいった。
「とりあえず、俺んちに行こう。話はそれからだ。さあ、乗れよ」
「乗れって、背中に?」
「ああ」
ルーキオがしゃがんでおんぶの姿勢をとった。渡はとまどいながらその背中におぶさると、ルーキオは渡のふとももを、がっちりとつかんだ。
「ゆれるから、しっかりつかまっとけよ!」
「わかった!」
渡は急いで、かばんについていた紐を腰にくくりつけた。
「じゃあいくぞ! それっ!」
はじかれたように、ものすごい勢いでルーキオの体が飛んでいき、目の前の景色がものすごい速さで通り過ぎた。再び目を開けると、渡はどこかのビルの屋上にいて、いまやルーキオは、更に高く空中に浮かぶビルへとジャンプしようとしていた。
「わぁ~っ!」
ルーキオは、斜めになっていた壁を走り抜けると、今度は飛び込みの姿勢で、下の屋根に向かって飛び降りた。そんな状態が5分ほど続いただろうか。このあまりのめまぐるしさに渡は気を失いかけていた。立ち止まった隙をなんとか見つけると、ようやく渡は口が利けるようになった。
「どこまでいくの?」
「もうちょっと。口を閉じとけよ。舌かむぜ」
ルーキオはそういうと、またもやジャンプした。
さらに飛び跳ねていき、3分ほどたった頃、ルーキオはものすごいジャンプをした。
それが最後のジャンプだった。ようやく目的地にたどり着いたらしく、渡は閉じていた目を開いた。そこは、はるか空の上の家だった。二人はベランダにいて、見たことのない文字のような形をした柵が周りを取り囲んでいた。かたまりになった風たちが、ヒューヒュー吹き渡っている。
「おい、ついたぜ。……おい!」
渡はぐったりしてしまい、何も答えられなかった。まさかこんな目にあうなんて……。
突然、ベランダのガラス戸ごしに、女性が近づいてきた。なんと、さっきの自転車の女の子だ! ガラス戸が、ガラッと開いた。
「ただいま」
「ちょっと、ちょっと! どうしたのよ!」
女の子は、ぐったりしている渡を見て焦っているようだった。
「どーしたもこーしたも……迷子さ」
「とにかく入んなさいよ」
ルーキオは渡を担いだまま部屋の中に入っていくと、渡を床におろした。渡はそのまま、仰向けに寝転がった。
「はぁー、つかれた」と、ルーキオが言った。
「それで? この男の子って——あっ!」
「そう、ネルルがひきかけた子だぜ。迷ってたみたいだから連れてきた」
ルーキオは、青い顔をしている渡をのぞき込んだ。
「大丈夫か?」
返事はなかった。目が回ったのか、クラクラしていた。
「かわいそうに……お兄ちゃん、無茶したんじゃない?」
ルーキオは目をつむり、寝たふりをした。
「お茶4つ、いれてくれない?」と、ネルルがいうと、ルーキオは目を開けてお茶をいれにいった。
ネルルは、改めて渡を見た。
(あれ? この顔……昔どこかで見たような)
ネルルは頭に手を当てて考えたが、思い出せないらしく、わずかに首を振った。
ネルルとルーキオは、この不思議な男をどうするのか、お茶を飲みながら話し合い始めた。
「まずは話を聞かないと。いったいどこの誰で、なぜ突然現れたのか……。謎ね」
「そうだな。記憶も見たい。記憶情報があれば、人物を特定できるだろう」
「ここでも見れるけど……やっぱり、センターに行った方がいいかも。ポコルンなら、正確な情報を教えてくれるはずよ……あ! 起きた!」
まだ頭はふらついていたが、渡は体を起こした。狼人間と、女の子がこちらを見ている。
「あっ! 自転車の!」
「また会ったわね」
「そういえば、どこかけがはないか? えーっと、名前は……」
「時野戸渡です」
「ときのと わたる? 変わった名前だな。なんて呼べばいい?」
「渡でいいよ」
二人の会話を聞いていたネルルの顔が、なにかに気がついたように、急に険しくなった。
「けがはないかって、どういうこと? 変身能力があれば、けがなんて……」
「ところが、わた……るは、変身能力を身に着けてないっていうんだ。俺も確かめたんだが、変身のことすら知らなかったぜ」
「うそっ! あなた、体は大丈夫なの?」
ネルルがすぐそばまで近づいてきたので、渡は慌てた。
「大丈夫。かすり傷もないよ」
「ごめんね。ほんとに大丈夫?」
「当たってないしこけただけだから、大丈夫だってば」
「一応、簡単な健康チェックをしとこう」
ルーキオは、丸いおまんじゅうくらいの大きさの機械を、渡の額に当てた。すると、一瞬ひやっとして、その10秒後には機械がピロン♪ と鳴った。
「オールクリア。異常は何もなしだ」
「よかった!」
ネルルが胸をなでおろした。
「——てことは、脳波や記憶も正常ということになるな……。お前に聞きたいことがたくさんあるんだが……」
「まあ、まずはお茶でも飲みなさいよ。座って」
白いテーブルの上にはお茶が置いてあった。そして、小さなカップのそばには、白いウサギのようなリスのようなふわふわした生き物がいて、渡の方をじっと見ていた。耳は、フェネックの耳のようにふわふわで、ただし、先の方はコアラのようにぼわんと丸くなっていた。
「おっと、紹介が遅れたな。こいつはグニュウ。センターで育った万能生物だ……って、そんなこと言ってもわからないか。まあ、俺たちの家族ってこと」
「へー、かわいいね」
「ニュウ!」
グニュウは器用にコップをつかむと、コップを傾け、お茶を飲み始めた。どうやらかなり賢いらしい。
渡は椅子をひいて座ると、得体のしれないお茶をのぞき込んだ。
なんだかこおばしい香りがする。
飲んでみると紅茶のような味でとてもおいしく、いれてから時間が経っているはずなのに、熱いままだった。
不思議なことに、一口飲んだだけで、めまいはほとんど感じないくらいましになった。
「それじゃ話してもらおうか。お前、どこから来たんだ? いったいどういう方法で突然現れた?」
「僕が聞きたいくらいだけど……」
渡はとまどいながらも、写真を撮りにやってきたこと、そこで占いの建物を見つけたこと、その占い師に水晶のようなものを見せられたこと、その水晶を見ていたら、街の景色が近づいてきて、気がついたらその街の中に入ってしまっていたことを話した。
それから、今は大学生で、日本の大学に通っているところで、授業を受けて、サークル活動やアルバイトをしていることを伝えた。
二人は熱心に渡の話を聞いてくれたので、渡は少しドキドキしつつも、心強かった。
ルーキオは、渡の言ったことを、頭の中で反芻しているようだった。
「——ふーん、そうか。渡が暮らしているのも、地球であることは間違いないだろう。
だが、今は4月だし、午後2時……ということは、時間も場所も違うところに来たってことになる。つまり……タイムスリップだ」
「タイムスリップ? この子が?」
「そう。それも偶然じゃない。その水晶玉が、タイムマシンの役割を果たしたと考えたほうがいい」
「けど、タイムトラベルするのには、タイムホールが必要よ? ホールもなしに、突然現れるだなんて……」と、ネルルがいった。
「そうだ、おれたちの現代の科学力ではそんなこと、できるはずもない。見るだけでタイムトラベルできるっていうことは、おれたちよりもはるかに科学技術が進んでいるという事になる……。
おい渡、おまえの時代じゃ、動物に変身するなんてこと、できないんだよな?」
「うん、そんなこととてもできないよ」
「やはりな。だとすると、思った通り渡は過去の人物ということになる。だが、その占い師というのは……俺たちより未来の人間かもしれない」
「未来の?」
渡とネルルの声がそろった。二人は、思わず顔を見合わせた。
「ああ。渡、おまえもなぜこっちに送り込まれたのか、心当たりはまるでないってことなんだな?」
「ああ。全くわからない」
「謎ね」
ルーキオとネルルは、真剣な表情で考え込んでいた。渡は、どうしたものかと二人を見つめていた。
「これはやはり、センターに連れて行った方がいいかもな。なにやら事件のにおいがする」
「そうね。ポコルンなら何かわかるかも」
「ル? ポコ?」
グニュウはポコルンの名前を聞いて、コップの取っ手の隙間から、ネルルをのぞき込んだ。
「なんらかの手がかりは絶対得られると思うわ。あとでいきましょ。……で、ずっと気になってたんだけど、背中に持ってるのは何? 何か入ってるの?」
「ああ、えーっと……」
渡はかばんに入っているものを出していった。
授業で使っている教科書に生き物の図鑑、ノートや筆箱、持ち歩いていたカメラと予備のフィルム、財布や携帯など。
ネルルは、知らないものが次々とテーブルに置かれていくのを、興味深そうに眺めていた。グニュウは筆箱のファスナーに気づいて、ぐぐっと引っ張って開けると、中のものを出し始めた。
「これは?」 ネルルはフィルムカメラを手に取っていった。
「カメラだよ。こうやって景色を写真に写すの。これが写真」
渡は何枚か写真を見せた後、カメラを手に取って、写真を撮る様子をみせた。ネルルたちは不思議そうにその様子を見ていた。
「のぞいてみる?」
渡がカメラを手渡すと、ネルルはおずおずとファインダーに目を近づけた。それから、ファインダー越しに部屋の中を見始めた。その時、窓の外を巨大な空飛ぶ電車が、ゴーッと通り過ぎていった。
「へー、おもしろいわね」
「つまり、俺たちの目と似たよう装置ってことだな」と、ルーキオがいった。
「目が、どうなってるの?」と、渡が聞いた。
「見たものはすべて、記憶できる。その記憶をもとに、機械を通じて映像として反映できるのさ。静止している映像でも、動いている映像でも……」
「すごい」
「ほかにもあるぜ。俺たちは、お前が普段話している言語を話してるだろ?」
「そういえば……どうして?」
「まず、おまえが叫んだ時に、お前の言語が無意識のうちに自動で検索された。俺たちは、相手が誰であっても、その言語に合わせて違和感なく話せるよう、自然に脳が作用するんだ。だが、文字はまた別だからな。
そこの本を後で貸してくれよ。文字も読めるようになっておきたい。
それはさておき……お前をセンターに連れて行かないとな」
「センターって?」
「人類の知識、生命の保管庫、研究所でもあり、進歩のためのすべてが詰まっている場所さ」
「だけど、僕、きみたちのことなんにも知らないよ」
「それは俺もさ。そして、おまえのことが分かる場所がセンターってわけなんだ。お前のことが分かれば、おまえが送り込まれた理由もはっきりするかもしれない。それに、お前もおれたちのことがわかるかも」
「じゃあ、早くいきたい!」
「もちろんだ。ただ、その前にひとこといわせてほしい」
「なに?」
すると、ルーキオは渡をしばらく見つめ、ニッと笑った。
「未来へようこそ」