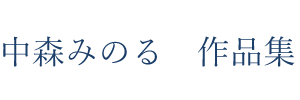第6章 カクウル
渡は車内を見渡してみた。中の様子は普段よく乗っている電車にどこか似ている。
乗客はまばらで、渡たちはすぐ近くの空いている席に座った。ネルルは膝の上にグニュウを乗せ、にこにこしている。席の後ろには巨大な横長で楕円の窓ガラスがあり、外の景色が良く見えた。
渡は、ようやく落ち着いて乗客に視線を投げかけた。本当は一刻もはやく、どんな人がいるのかみたかったが、あんまりじろじろ見るのも気が引けていたのだ。
真っ先に目に入ってきたのは、綿あめのかたまりのような羊2頭だった。どちらも眠っており、右の羊は女の子に抱きしめられていた。羊を抱きしめた女の子のとなりは、そのお兄さんらしき男の子が座っていて、二人は人間だとはっきりわかった。その子たちの前には、頭は鳥で、体は人間の恰好をした鳥人が、二本の吊革を鉤爪でつかんでぶらさがっている。
男の子のとなりには、水色の丸いソーダアイスクリームのような物質に包まれた人物が、退屈そうにすわっていた。その右となりには、桃色のおおきなウサギのぬいぐるみが置いてあった。ところが、これはたんなるウサギのぬいぐるみなのか、それとも、ぬいぐるみに変身した姿なのか、一切動かないので渡にはわからなかった。
半透明の濁った水のように見える人物や、眠り続けるコアラに半分変身した人など、車内は眺めるのに飽きなかった。
駅などはなく、空中に停めてあった別の乗り物や、渡たちのような空飛ぶ家など、乗客は思い思いの場所で降りていった。まるで大人数で乗るタクシーみたいだなと、渡は思った。
窓の外では、来た時と変わらず、いろんなものが通り過ぎていった。なかには列車よりもはるかに速いスピードで飛び去っていくものもあった。窓からは夕日が差し込んでいて、渡はそのみなれた光景をみて、どこかほっとした気持ちになった。
「ポログレイン様、御一行様。間もなく到着いたします」
みると、ネルルたちの家はもうすぐそこに見えていた。列車は横に滑るように動き、ベランダの柵のとなりに、見事に横づけされた。乗る時と同様、通路が、今度は階段状に伸び、ベランダの中にまで続いた。3人は手すりをつかんで降りて行った。
「ご乗車ありがとうございました」
通路が引っ込んだ後アナウンスが流れ、列車は再び滑るように動き出した。渡は、夕日に包まれた列車が静かに遠ざかっていくのを、じっと見つめた。
「着いたな。とりあえず、お茶でも飲むか」
ルーキオはベランダの窓をガラガラと開けて部屋の中に入ると、お茶をとりにいった。渡は椅子に座ると、今までの疲れがどっとあふれ出たような感じがした。
ルーキオが、コップを抱えて戻ってきた。グニュウの分の小さいコップもある。
「グニュウはお水ね」
「ウ」
グニュウはコップを器用に持ち上げて、こっくんこっくん飲み始めた。渡も飲み始めると、中身はお茶じゃなく、もものような甘い味のする果物のジュースだった。
「おいしい?」と、ネルルはグニュウに聞いた。
「ニュウ!」
グニュウはコップを高々とかかげ、ばんざいした。ルーキオも、一息にジュースを飲み干すと、ふーっと息をついた。
「それで、これからどうする? もうすぐ夜だけど……」と、ネルルが聞いた。
「明日の予定を立てるか……。一応明日の朝までにはタイムマシンが届くだろう」
「え~、明日もう過去に行くの? つまんない」
「まあ、すこし早いか……。渡はどうしたい? もし望むならいくらでも、こっちにいていいんだぜ」
「ほんと?」
「ああ」
渡は、元の時代に帰ったら、3日後にサークル旅行があることを考えていた。2泊3日のサークル旅……その旅を最後に、雪村まりんとはもう会えなくなるだろう。心の準備はできていたはずだった。だが、いくらでも先延ばしにできるかもしれないという状況にいざなってみると、心はたちまちぐらついた。
(どうしたいんだろうか? 後回しにしたいんだろうか? それとも……。そもそも別れの覚悟はできていたんだろうか。だいたい、ネルルとのことを考えたら、もう……)
渡はじっと思いをめぐらした。
「一ヶ月ほど、こっちにいたい。過去に戻るのは、それからでもいい?」
考えはまとまらなかったが、渡はそうお願いした。
「やった!」と、ネルルが言った。
「いいぜ。じゃ、そうするか。過去にはいつでもいけるからな」ルーキオはあっけらかんと言った。
「ええ。じゃ、この一週間どうする? センターには行ったわけだし……」
「街に繰り出すのもおもしろいかもな。見たことのないものがたくさん見れるはずだぜ」
「そうね。カクウルだとか、ダルーマ・シアンだとか、見せたい町はたくさんあるもの」
「カクウル? どんな場所?」
「いっちゃったら面白くないでしょ」
「そっか。じゃあ、カメラって持って行っていい? 写真が撮りたいんだけど……」
「タイムマシンで過去に持って帰るつもりみたいだけど、未来の映像は持ち帰れないわ。——それより、お腹減ってない?」
「うん」
「おれたちはどっちでもいいんだけど、渡は必要だもんな。何か食べよう」
ルーキオは、壁に埋め込んである電子レンジのような機械のところへいくと、中に皿を3ついれて、少し考えボタンを押した。
「オムライスを3つにしよう。 温度は60℃で」
「どうなってるの?」
「素粒子組み立てで料理が作れるのさ」
渡は立ち上がってレンジをのぞきこむと、中はまるで濃霧に覆われているようだった。
中で素粒子組み立てというのが起こっているのだろうか、紙が灰になるのを逆戻しで見ているみたいだった。まずケチャップライスが皿の上に集まってきた。かと思うと、黄色い卵がもう暖かい状態で乗っかっていた。時間にして3分ほどだろうか?
出来上がった時には、レンジの中の霧はすっかり晴れていて、出来立てほやほやのオムライスがそれぞれの皿のうえに乗っていた。デミグラスソースまでついている。
スプーンと一緒にテーブルの上に運んでくると、グニュウはオムライスから湧き上がる湯気をじーっとみていた。
「いつもながらふわとろだな。食べよう」と、ルーキオが言った。
渡はまた椅子に座ると、オムライスを見つめた。本物とそっくりだ。というより、こちらもまた本物ということなんだろう。スプーンでオムライスをすくうと、チキンライスの中には鶏肉としか思えないものもあった。食べてみると、お肉そのものだった。
「おいしい! 」
渡は一口食べて、ずいぶんお腹が減っていたことに気がついた。一口ジュースを飲むと、渡は夢中で食べてしまった。最後にごくごくとジュースを飲み干すと、ふーっといきをついた。
「ふふっ」
ネルルがこっちを見て笑った。渡は思わず恥ずかしくなった。
「ごめんね、おもしろくって! ——グニュウ、まだ欲しいの?」
ネルルがグニュウの前にスプーンを持っていくと、グニュウはオムライスをつかんでほおばった。
「食べて落ち着いたか?」と、ルーキオがきいた。
「うん」
「それじゃ、食べた後はこれよ!」
ネルルは飴玉のようなものが入った瓶を取り出した。
「手を出して」
言われるまま手を差し出すと、手の中にコロンと飴玉のようなものが落ちた。
「なにこれ?」
「これをなめたら、口の中がすっかりきれいになるのよ。こうやって……」
ネルルは、手本を見せるといわんばかりに、飴玉をポイッと口に放り込むと、もごもごと一生懸命なめだした。渡はなんだか笑いそうになるのをこらえて、ネルルをじっと見ていた。
「——もうちょっと。……ほら!」
ネルルは口を開けて、歯の様子を渡に見せてきた。興味深くネルルの口の中をのぞきこむと、確かに何の汚れもなかった。
「へぇー、ほんとだ」
渡が感心してみていると、ネルルは急に恥ずかしくなったのか、パッと口に手を当てた。
「ちょっと! あんまりじろじろ見ないでよ」
「でも、ネルルが見せたんでしょ」
するとネルルは赤い顔のまま、顔をしかめた。
「……ふん! まあいいわ!」
渡は、居心地が悪くなってうつむいた。すると、だんだんトイレに行きたくなってきた。そういえば、もうずいぶん行ってない気がする。
「ねえ、トイレってある?」
すると、ルーキオがにやにやしながら答えた。
「あるぜ。部屋を出たら廊下をまっすぐいって一番奥、右側だ。シャワーをあびたけりゃ、トイレの向かいにある。下着も服も、いつも新しいのを予備においてあるから、それを使えばいい」
「わかった。ありがとう」
渡はそそくさと立ち上がると、廊下に出て、トイレへと向かった。
部屋が向かい合うように6つあり、どれも扉が閉まっていた。トイレに関しては、現代とあまり変わらないような気がした。用を足していると、なんだか疲れを感じていた。渡は、鏡つきの洗面台で手を洗ったあと、ふと気になって歯を見てみると、驚いたことに、虫歯になりかけていたところがすっかり治っていた。
ずいぶん汗もかいたので、シャワーも浴びることにした。脱衣所があって、袋に新しい下着や服が、たくさん入っていた。これがルーキオの言っていた備品だろう。
シャワーは水が細かく、肩にあてると、すごく凝りがほぐれていくような感じがした。渡は一人でシャワーを浴びていると、こんな場所にいるのが不思議だと思うと同時に、なんだか冷静な自分がいることに気づいた。すると、ネルルといて、なんだかドキドキしてしまうことを、認めないわけにはいかなかった。ふと、雪村さんの顔が浮かんだ。渡はぼんやりと、シャワーの水をみつめた。
部屋に戻ると、ネルルとルーキオがなにやらこそこそ話していたが、渡に気がつくと話をやめた。
「場所分かったか? お茶あるぜ」
ルーキオは、温かいお茶をすすめてくれた。お茶をゆっくり飲んで、今日のことに思いをはせていた。あたりはすっかり夜だ。疲れからか、いまにも寝てしまいそうだ。
「なんだか眠くなってきた」
「それじゃ、今日はもう寝るか。こっちだ」
渡は再び廊下を歩いていった。ネルルはグニュウを抱えている。
「こっちが俺の部屋で、こっちがネルルの部屋」
ルーキオは、廊下に出て左側、リビング寄りの部屋を指さし、次に右の部屋を指さした。
「渡には来客用の部屋を使ってもらおう。俺の向かいの部屋」
ルーキオは、部屋に入っていくと、パチッとスイッチを押した。部屋は明るくなって、左側に大きな二段ベッドが置いてあるのが見えた。
「ほとんど使ってないが……上と下、どっちがいい?」
「上かな」
するとルーキオは、はしごをのぼって、マットやまくらをさわってチェックした。
「まあ大丈夫だろ。寝巻はそれでいいし、明日からはポコルンがくれた服を着たらいい。そこの棚に置いてある」
みると、白いシャツと青いズボンが、棚の上に置いてあった。
「明日からいろんなところに行くだろうから、今晩はゆっくり寝ろよ」
「うん。ありがと」
ルーキオが部屋を出ていくと、渡はさっそくはしごをのぼっていった。
奥まっていたせいで気がつかなかったが、ベッドの横にあるはずの壁は、一面窓になっていた。
ガラスは、下のベッドまで続いていたが、床から30センチほどは壁になっていたので、上の方が景色が良く見えるのは間違いなかった。
外を見ると、部屋から漏れるあかりに照らされた雲が、ゆっくり流れていく。もう今日か明日には満月のはずだが、月は雲に隠れているのか、見えなかった。渡は布団をかぶると、すぐに眠ってしまった。
◇
朝が来た。目を覚ました渡がふと窓の外を見ると、不思議なことに、あたりは森の中だった。渡は森の様子を眺めながら、信じられない気持ちで景色を見ていた。
(また何か、おかしなことが起きているに違いない)
はしごをおりると、とりあえず、おいてある服を着た。
「おはよう。起きたか?」
ルーキオがいつの間にか部屋の中にいて、渡を見上げていた。
「おはよう。ねえ、どうして森の中にいるの?」
「家ごとワープできるのさ。カクウルは遠いから……ここはもうカクウルの中だぜ」
「えっ? ここがもう?」
渡は改めて森の中を見た。リスのような生き物が、すばやく木をつたっていた。未来にあっても、ちゃんと自然が残っているんだ。渡は安堵していた。
「カクウルは小さな大陸で、大きさは320万平方キロメートル。人工知能や高機能機械を拒絶した人たちが暮らしている。地球人口の20パーセントがここにいるんだ。カクウルみたいな場所は地球上で他にもいくつか点在しているが、中でも人口が一番多いのがここだな」
「へぇ~」
話し声を聞きつけたネルルが、グニュウと一緒に部屋に入ってきた。
「おはよー。今日はカクウル巡りね。ざっと見てまわるのなら、ワープゲートを使うのがいいかも」
「そうだな。ゲートを3つまわっていけば戻ってこれるか。とりあえず、顔を洗ったら外に出よう」
「ニュウ」
「そういえば、タイムマシンってどうなったの? もう届いた?」
「ああ。朝一番に、ポコルンがワープホールをくぐって届けてくれたぜ」
「ワープホールをくぐった?」
「ああ。ポコルン型ロボットは高機能だから、ワープホールを出せるんだ。生き物を通せるワープホールを出すこともできる。ま、審査は通ったってことだ」
「よかった」
「ああ。でもまあ、むこう3週間は、タイムトラベルのことは考えなくていい……詳しいマシンの使い方は、おいおい説明しよう。説明してもどうせ忘れるだろうから」
「わかった」
渡たちは顔を洗った後、テーブルに座ってお茶を飲んだ。
「ウゥ?」
ふとテーブルの上に目をやると、グニュウが渡の頭を見ていた。どうも寝ぐせが気になるようだ。と、その時、グニュウの体からニョキッと翼が生えた!
「ニューウッ!」
グニュウは勢いよく後ろ足でジャンプすると、翼をはためかせ、渡の頭の上に飛び乗った。渡は、グニュウが落ちてしまわないように、手でそっと支えた。ふわふわやわらかく、ムニュッとしている。グニュウは渡の髪の毛を、めいいっぱい引っ張った。
「いたた!」
「ウゥ……」
グニュウのひっぱりが少し弱まった。グニュウは髪の毛を離すと、今度は渡の髪の毛の上でクロールの真似をし始めた。
「ルッ! ルッ!」
渡は、頭から落ちないかと気が気でなく、両手の指先を合わせて何とかしのいだ。ネルルはぼんやりとそんなグニュウの様子を眺めていた。
「ずいぶん気に入られたみたいね」と、ネルルが言った。
「なんだ、ネルル、やきもちか?」と、ルーキオがからかった。
「そんなわけないでしょ!」
ネルルは顔を赤らめて怒った。
渡は、なぜかモコのことを思い出していた。すると、どうしたわけか、グニュウと一緒に遊んではいけないような気持になって、つい、グニュウをつかんで、ネルルに渡した。
「ル? ル?」
グニュウは、どうして引き戻されたのかわからず、不思議そうに手足をばたつかせた。
「どうしたの? 痛かった?」と、ネルルが聞いた。
「いや、そういうわけじゃないんだけど……」
「じゃあどうして?」
渡は、何も答えられずに、ただグニュウを押し付けるようにネルルに渡した。ネルルの顔が、とたんに曇っていった。グニュウもすっかり拗ねている。
「……まあいいじゃねーか。早くカクウルにいこうぜ」
「そうね。……知らない」
ネルルは、つんつんしたままベランダを出ていった。ルーキオも渡に一瞥をくれただけで、そのままベランダから出て行ってしまったので、渡はあわててその後をついていった。
森の中は開けていて、小道が続いていた。渡は、ここが未来だとは思えないくらいだった。あたりからは鳥の鳴き声が聞こえてくる。木漏れ日が差し込んでいて、湿った空気があたりを包み込んでいた。
グニュウは、ネルルの腕から飛び出して、ぴょんぴょんそこらを跳ね回った。花も時々見かけた。名前がわからないだけで、渡が知っているような花もたくさん咲いていた。
10分ほど歩いていくと、森を抜けた。すると、目の前には田園が広がっていた。ちょうど田んぼに水がはっていて、空が映りこんでいる。田んぼの向こうにはところどころ家が見え、知っている田舎の風景とそっくりだ。ネルルとグニュウの機嫌は、ありがたいことに、森を歩くうちにずいぶんよくなっていた。
「いつみてもすごいわねぇ」と、ネルルが感心した。
「なんだかなつかしい気持ちになるぜ。自分で育てて食べる……そんな時代がずっと続いていたんだ」
その言葉を聞いて、渡は気づいた。今や簡単に料理が作れる……それどころか、食べる必要さえないかもしれない時代なんだ。
田んぼのあぜ道を歩いていくと、やがて川が見え、水車小屋が見えた。水車は手作りのようで、ごうんごうんと音を立てて回っている。3人は、しばらく水車を眺めてから、小屋の中に入っていった。
「一つ目のゲートはここ」
ネルルが、まわる臼を横目に、水車小屋の外に通じていらしい扉を開けた。扉は確かに外に通じていた。だが、そこはさっきの田園風景ではなく、屋台街か露天商のような場所だった。人でにぎわいかえっていて、がやがやとしている。驚いて目を見張る渡を、二人は面白そうに見た。
「お店をやってる! 何を売ってるの?」
「売ってる? ちがうな。ただで譲り受けるだけさ。交換っていうのもあるが。だいたいが手作りの品だ。うんと時間をかけたものもたくさんあるんだぜ」
「へぇー」
見てみると、高価そうな織物や手書きの絵画、陶芸作品、絨毯、あらゆる大きさのぬいぐるみ、バッグや小物入れ、ドライフラワーやリース、大型の家具、竹細工、色とりどりの宝石、そして見たこともないような料理が並んでいた。ふらふらと進んでいきそうになる渡の手を、ネルルがつかんだ。
「ちょっと待って! ここでコインを取っとかないと」
みると、すぐそばの大きな箱の中に、山ほど金色のコインが入っているではないか?
ネルルがコインを掬い取ると、平らだったコインに、不思議な文様が刻まれた。渡も手に取ってみると、コインは変形し、ネルルとはまた別の文様になった。ルーキオは、目いっぱいコインをつかむと、無造作にポケットに入れた。
「これって何なの?」
「まあ、見てればわかるさ。こっち」
ルーキオは、ぬいぐるみ屋の前に立ち止まると、店の人に話しかけた。
「やあ、デリダ。調子はどうだ?」
すると、デリダと呼ばれた女の人が、ぬいぐるみを縫う手を止め、顔をあげた。
「あら、ルーキオじゃない。元気よ。なにか欲しいものある?」
「そうだな……そこの、ウサギのぬいぐるみをもらおうか。うまそうだ」
ルーキオは白いウサギのぬいぐるみを手に取った。
「いいわ。金貨8枚ね」
「はいよ」
「ありがとう」
ルーキオは金貨8枚を渡すと、店主はそれを受け取った。店主がぬいぐるみをさわってからコインに触れると、不思議なことに、文様のない反対側に店主の文様が浮かび上がってきた。その模様は、どことなく、ウサギの顔に見えた。ルーキオはウサギのぬいぐるみを受け取ると、店を後にした。
「ははは、いいものがもらえたぜ!」
ルーキオは上機嫌だ。グニュウはウサギのぬいぐるみを興味深げに見ていた。
「さっきのってなんだったの? コインの取引みたいな」と、渡が聞いた。
「あれか。ああすることで、誰がどの品を買ったのか、わかるようになってるのさ。あのコインは、この世に二つとない代物になったんだ」
「でも……それって何かの意味があるの? コイン自体に付加価値がつくとか?」
「意味や価値? んー、誰が自分の品を持って行ったのか、証明になるだろ? コインをたくさん持ってるってことは、それだけ自分の作ったものが受け入れられた証になる。彼らはそれが喜びなんだ。ただ、一年で使えるコインの枚数には限りがあるぜ。1000枚まで。どうしても1000枚を超えて使いたい場合は、複雑な申請がいる。その申請に通っても全部で1100枚が限度だし、最後の100枚は使っていい商品も限定される。一人にもっていかれちゃ、つまらないからな」
「へぇ~」
「人間の尊厳とでもいうのかな。ロボットや機械の手を借りず、自分の力で作り上げる……さらにそれが認められる……そういう価値を、彼らは大事にしているんだ。もちろん、俺もな」
「なるほどねえ」
「だから、どんどん貰ったほうが、ここじゃ喜ばれるぜ。渡、コインが少ないんじゃないか? コイン箱はあちこちにあるから、補充しとけよ。1000枚以降は、取ったところで文様は浮かび上がらず、使えないが」
「わかった」
それから3人は、気に入ったものを見つけては、じゃんじゃん金貨で譲り受けた。気に入った客じゃないと譲らないという人もいるらしかったが、渡がルーキオとネルルの知り合いという事で、譲ってくれる人ばかりだった。
渡は最初、自分のお金でもないのにただで譲り受けることに罪悪感を感じていたが、売る人がみな喜んでくれていたので、そのうちあまり気にならなくなった。食べ物は大体金貨1枚か2枚だった。渡は、あれもこれも欲しくなって、食べきれないほどの料理を譲ってもらった。
水色のわたあめのようなものを食べていると、グニュウが肩を渡って顔を寄せてきたので、渡はあわててわたあめを遠ざけた。
「ウルルルル!」
グニュウは不満そうだ。
「ネルル、グニュウってこれ食べられるの?」
「心配しなくても、ここにあるもの全部、グニュウなら食べられるわ」
「そう」
渡は、わたあめをグニュウの方へ傾けた。すると、グニュウはたちまちにこにこ顔に戻って、わたあめによじのぼってかぶりついた。
「ふふふ!」
ネルルが笑って、持っていたピンクのわたあめを、水色の綿あめにくっつけた。グニュウは、ピンクと水色のわたあめを、交互に食べだした。渡もわたあめをつまんで食べると、ふんわりしていておいしかった。
「あ! ドウ爺さんが店を出してる!」
ルーキオが不意に走り出した。ルーキオは連なる店を通り過ぎ、ある店の前で立ち止まった。立派な屋根がついている。店の前には大小さまざまな額があり、どうやら絵が作品らしい。
渡は、店の前に来てみて、絵を見て驚いた。なんともすばらしい波の絵や風景画などが、ところせましと飾られている。一枚欲しくなって、額についた値段を見て驚いた。一番小さなものでも、金貨1万枚必要だったからだ。
「調子はどうだ? 相変わらずもらわれないか?」
すると、ヒゲだらけのドウ爺さんは、顔をしわくちゃにして笑った。
「ひゃっひゃっひゃっ! 金貨の使い道のわからないやつばかりでな。最後に譲ったのは38年前、これっぽっちの小さい絵だったかのう」
「そうか。俺も欲しいんだが、目に焼きつけるだけでがまんしているのさ」
「ひゃっひゃっ! それもよかろう!」
ドウ爺さんは、特に気にした様子もなく笑っていた。
ドウ爺さんのかけているエプロンは、ありとあらゆる色の絵の具がついていた。渡は、大小さまざまな絵に目をやった。どれも素晴らしいものだったが、中でも、奥にある一番大きな絵に圧倒された。朝日が差し込んだ巨大な山の絵だったが、渡がこれまで見たありとあらゆる絵の中で、最も静かな迫力があった。
こんなすごい絵を、このおじいさんが描き上げたんだろうか? そうに違いない。渡は、尊敬のまなざしでおじいさんを見た。
「だけど、値段がな。一番奥のは、確か完成するまでに200年かかったんだっけ?」
「そうじゃよ」
「うーん……。妥当だとは思うが、なにしろ30万金貨だろ? 誰にも手が出せないぜ」
「いいんじゃよ。ここに来てくれた人が見ていってくれたら」
渡は、ドウじいさんの太っ腹な精神に感心した。
「ははは、恐れ入るぜ。おれたちにとってはありがたい話だ。——じゃあ、また来るぜ」
「ああ、いつでもおいで」