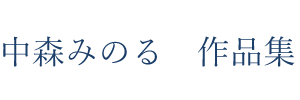ドウ爺さんと別れてしばらく行くと、店と店の間に、不思議な扉があった。
「これが2つ目のゲート。200km離れたカクウルの街につながってるわ」
ネルルはゲートを開けると、オレンジがかった赤い屋根がそこかしこに見え、間違いなく街中だった。振り返ると、扉は街路樹と街路樹の間に、不自然に取りつけられていた。通り抜けると、美しいヨーロッパの街並みの中に、突然迷い込んだような気持になった。
10才くらいの子供たちが5人、しゃぼん球を飛ばしながら、街の中を走り回っていた。ここが同じ未来だなんて、信じられない。子どもたちは、木がたくさん生えている、大きな公園の方に向かっていった。
「行ってみる?」と、ネルルが聞いた。
「うん」
公園の中に入ると、様々な遊具、そして遊んでいる子供たちが見えた。鬼ごっこをしているように見える。ちょうど近くにベンチがあったので、3人はそこに座って、子どもたちの様子を眺めていた。
「ルルイ」
グニュウが、屋台でもらった食べ物をごそごそとさわりだした。どうもわたあめだけでは足りなかったらしい。
「おなかへってるの? みんなで食べようか」
渡がみたこともない料理を膝の上に広げていくと、グニュウは夢中で食べ始め、ネルルやルーキオも一緒に食べだした。遊んでいた子供たちも、においにつられたのか、もの珍しそうに近寄ってきた。
「こんにちは。それってラーグ通りでもらったやつ?」と、男の子が言った。
「そうだよ」と、渡が言った。
「いいなぁ。僕たち、もう今年のコイン使いきちゃって」
「食べる? たくさんあって、食べきれないかもしれないんだ」と、渡が言った。
「いいの? それじゃ、もらっちゃお!」
後ろに隠れていた子たちも出てきて、みんなに料理が手渡されていった。スプーンやフォークも人数分あって、わいわいがやがや、まるでピクニックに来たみたいににぎやかになった。
「ネルルお姉ちゃん、それ、おいしい?」と、女の子が聞いた。ネルルは、いももちのようなものを食べようとしていた手を止めた。
「おいいしいわよ。はい!」
ネルルが女の子の口元にいももちを持っていくと、女の子はパクッとかぶりついた。いももちは、びよーんとのびて、そこをグニュウが飛びついて食べた。
「あはははは!」
「レレレ! レレレレレ!」
グニュウは満足げに笑うと、子どもたちは珍しそうにグニュウを見た。
「その子って……もしかして、人工生命体?」
「そうよ。グニュウっていうの」
「ほんと? 初めて見た!」
グニュウは、いっせいに子供たちにとりかこまれた。
「ウ!」
グニュウは、子どもの頭に飛び乗ると、また次の子の頭へ、次の子の頭へと、頭渡りを始めた。子どもたちはおかしくって笑った。次に、グニュウを捕まえようとする遊びが始まった。
「リ! ム! グ! リ!」
「えいっ」
「それっ!」
「あっ!」
「おっと!」
グニュウは飛び交う指の隙間を器用にくぐり、次の子の頭へと飛び移った。子供たちもグニュウも、この遊びが気に入ったようだった。グニュウは7回ほど往復すると、最後にばっと渡の方へ飛び出した!
「ウ!」
「わっと!」
グニュウは、ネルルと間違えたのか、しまった……という顔をしていたが、さすがのグニュウも息を切らして、渡の腕の中で動けなくなっていた。渡は、どうしたものか……ネルルに渡してしまおうか……と思った。すると、そのとたん、心をわしづかみにされたような、悲しい気持ちになった。
(なぜ? どうしてそう思ってしまう? 僕はこの先いつまでも、本当は大好きなものを、遠ざけて生きていくしかないんだろうか? )
渡は、胸の中からこちらを見上げるグニュウを見た。突然、花火がはじけるようにモコのことを思い出した。モコがいなくなってから、ずいぶん長い間、自分の気持ちに蓋をしていたことに、渡はようやく気がついた。
渡は意を決すると、ふるえる手の上にグニュウを乗せた。それからそっと頭の上に乗せた。ネルルもルーキオも、驚いた様子で、渡を見守っていた。グニュウは、ちょっと戸惑ったようだが、しばらくすると、鳥みたいに、髪の毛の中に、居心地のいい巣を作りはじめた。すると、何かのわだかまりが、少しずつ溶けていくのを感じた。
「あー面白かった! おにいちゃん、ありがと!」
「でも、そろそろあれやろうぜ」
「うん、あれやろ!」
「今日は馬になって、街の一番上まで競争!」
「うん!」
子どもたちは、今度は変身遊びを始めた。あれよあれよという間に、広場に5頭の仔馬が現れた。一頭だけは、どうしたわけか、しまうまだ。仔馬に変身した子供たちは、ベンチのまわりをからかうようにぐるぐるまわったあと、砂埃を立てて、公園の中を走り回り始めた。渡たちは呆気にとられてその様子を見ていたが、とうとう競争が始まったらしく、公園を抜けて街の坂道を、嵐のように駆け上がっていく。渡は、不思議な夢でも見ているみたいに、呆気にとられていた。折しも、背後から夕日が差し込んできた。上り坂の石畳が、夕日に照らされて輝いていた。
「グニュウ、あずかろうか?」と、ネルルが言った。
「ううん……このままがいい」
「ニュウ」
「そう。じゃあ、お願いね」
「うん」
ネルルがにこっと渡に笑いかけたので、渡はドキッとした。
「三つ目のゲートはこの先にあるけど……まだ時間があるな。森に戻るだけだし、どうせならもう一度ラーグ通りにいかないか? 晩御飯もほしいしさ」と、ルーキオが言った。
「賛成!」
3人は連れ立って街の中を歩いていき、街路樹と街路樹の間の扉をくぐった。屋台街のラーグ通りに出たとたん、おいしそうなにおいであふれかえっていた。渡たちは、さっき買いそびれた料理をたくさん買いながら、来た道を戻った。
ところが、少し歩いたところで、何やら、がやがやと騒がしい様子だった。渡は、つま先立ちして何が起こっているのか見てみると、どうやら一つの店の周りに、人だかりができているらしい。ルーキオも背伸びして、様子をうかがった。
「おい! ありゃドウ爺さんの店じゃないか? もしかして、絵が譲られるかもしれないぜ!」
ルーキオはそういうと、人込みをかき分けかき分け、ずんずん進んでしまった。
「ちょっと!」
渡は、置いていかれないように、慌てて後を追った。
「待って!」
ネルルがはぐれそうになっている。渡は思わず手をつかむと、ぐんぐん先へ進んでいった。
人込みをかき分けかき分け進むと、思った通り、人だかりの原因はドウ爺さんの店だった。ドウ爺さんはさっきと変わらず落ち着いた様子で、小さな男の子と話している。さっき公園にいた子供たちよりは大きかったが、それでも14才くらいだろうか。どういう取引が行われているんだろう……と、渡は耳をそばだてた。
「では、君は一番奥の絵を譲り受けたい……そういうわけじゃな?」
「ええ、そうです」
あたりでざわめきが起こった。そんなことがあるはずないと、みんな思っていた。なにしろ、金貨30万枚、つまり300年もの長い間、ここで買えるすべてのものを我慢して貯めないと買えない代物だからだ。
「値段は知ってるんだろうね? 300年間変わらず、金貨30万枚じゃが……」
「ええ。一年も無駄にせず、貯めに貯めました。ご存じでしょうが、1000枚の金貨は、このクリスタルのコイン1枚と交換できる……見ていてください。きっちり300枚あるかどうかを」
「なんと……!」
男の子が、持っていた袋を探って、テーブルの上にクリスタルのコインを10枚ずつ並べ始めた。周りの人は、その様子をかたずをのんで見守っていた。
20‥‥…60……。
コインが10枚ずつ同じ高さで置かれるたびに、ざわめきが一層大きくなった。
90‥‥…130……。
観客の一人は、目の前の光景が信じられないのか、ぎゅっと目をつむっている。
170……210……。
少年はペースを緩める気配もなく、淡々と置いていく。いつしかあたりは静まり返っていた。
250…………270……280……290……。
少年は、最後の10枚を、1枚ずつ置きはじめた。みんなの視線は、少年の手にくぎ付けだった。
4……5……6‥‥‥7‥‥‥8‥‥‥9‥‥‥……10!
とうとう、300枚のクリスタルのコインが、ドウ爺さんの机に積み重ねられた。
「ぴったり300枚です」
一瞬、あたりは誰もいないのではないかと思うほど、しんと静まり返っていた。だが、その次の瞬間、割れんばかりの拍手と歓声が沸き起こった。
ドウ爺さんは信じられないのか、さすがにいつもの落ち着きを失っていた。
「——あぁ!」
ドウ爺さんから、感嘆の声が漏れた。ドウ爺さんは、少年の方へ手を伸ばしたが、その手はぶるぶる震えていた。ドウ爺さんは、信じられない光景を見たかのように、目の前に輝くコインをじっと見つめている。
「……あなた、おいくつかね?」と、ドウ爺さんがたずねた。
「実年齢は314歳です」
「すると、14歳のころから?」
男の子は、だまってうなずいた。それを聞くと、ドウ爺さんの目から涙が流れ始めた。
「あっ! 思い出した! あの時の、君が……!」
ドウ爺さんは、とうとう顔を覆って、大泣きし始めた。男の子は、にこにこその様子を見守っていた。周りにいた観客も、ドウ爺さんを見て、思わず泣き出した。ドウ爺さんの絵は、滅多にもらわれないことで有名だったからだ。ドウ爺さんは、涙にぬれた手で、男の子の手をがっしりつかんだ。
「よくぞ……! よくぞ、長きに渡り、待っていてくださった! あなたに! あなたに……お譲りしましょう!」
ドウ爺さんが絞り出すように言うと、拍手喝さいが沸き起こった。男の子の目にも、ついに涙がにじんだ。固い握手がひと段落すると、ドウ爺さんは、絵に触れ、次にコインをさわっていった。すると、コインには、とびきり美しい紋様が浮かび上がった。
「俺が運ぶ!」
「俺も!」
「私たちも運ばせて!」
一番奥にしまい込まれていた巨大な絵は、観衆のうち4名が名乗り出て、丁重に店の外へと運ばれた。みんな気が付かなかったが、道には、絵を運ぶための荷車がちゃんと用意されており、その車の中へ、絵は降ろされた。まるであつらえたかのように、額はピッタリと荷車に収まった。
「今日はありがとうございました。また来ます」
男の子は深々とドウ爺さんにお辞儀すると、しゃがんで荷車の取っ手の中に入った。そして、緊張した面持ちで歩き始めた。店の周りに集まった人たちは、荷車が小さくなっていく様子を、じっと最後まで見守っていた。
「やったな! 爺さん!」
とうとう男の子が見えなくなると、ルーキオがドウ爺さんの肩をたたいた。ドウ爺さんは、何も言わず、にっと笑った。ドウ爺さんを心密かに尊敬している他の店の人たちにとっても、喜びはひとしおだった。ただ、いまや彼らはドウ爺さんを尊敬するだけではなかった……いまや、ラーグ通りで一緒に店を並べていることを、とても誇らしい気持ちになっていたのだった。だけどそれは、絵が譲られたから、というわけではなかった。
「渡、痛い……」
渡は、ふと我に返ってとなりを見た。ネルルの手をずっとつかんだままだった!
「ごめん!」
渡はすぐに手を離した。ネルルはさっと、手をポケットに入れた。
噂はすぐにラーグ通りのすべての店に広まった。そして、自然とドウ爺さんのお祝いパーティーが通りの近くの広場で始まった。
キャンプファイヤーがたかれた。渡たちも参加し、食べて祝って騒いでいると、もうあっという間に夜だった。上を見上げると、満天の星空が広がっていた。渡は星を見ながら、この日のことを、生涯忘れないだろうと感じた。
お祝いは一晩中続きそうだったので、3人は途中で切り上げて帰ることにした。森の中を歩いていると、葉っぱの隙間から、星がチカチカ光って見えた。
「ドウ爺さん……よかったわねぇ」と、ネルルが言った。
「ああ」と、ルーキオもしみじみ言った。
「でも、あの子っていったい誰なのかしら?」
「さあな。たまたま1年目に見つけたんだろう。だが——ははは、ほんとに子供の頃からため続けるだなんて、恐れ入るぜ! 金貨を使いたいと思った時もたくさんあっただろうに……」
「ほんと。僕なんて、今日だけでもう80枚くらい使っちゃったもん」と、渡が言った。
「ふふ、使い過ぎ!」と、ネルルが笑った。
家に帰っても、3人の中にはまだ興奮が残っていた。ドウ爺さんの長年のファンであるルーキオは、彼が今までに描いてきた絵のことや、どんなふうに創作活動をしているのかとか、あの博物館にはドウ爺さんのあの絵が飾られているだとかをこと細かに話してくれた。でも、今日起こったことはドウ爺さんの創作が認められたことの中でも、もっとも輝かしい事の一つにちがいないとルーキオはいった。
グニュウは、ふんふんと話を聞くふりをしながら、ふくろをあけて、持って帰った食べ物に手を出そうとしていた。
「ダメ! グニュウちゃん! 今日はいっぱい食べたでしょ!」
「ウルゥ……」
グニュウはすこし不満気だったが、確かに体が一回り大きくなっていたのを自覚していたらしく、しぶしぶ諦めた。渡は、楽しかった分、一気に疲れが押し寄せてきた。そこで、昨日のように、ネルルに歯磨きトローチをもらうと、シャワーを浴びて眠りについたのだった。
次回 7章 1