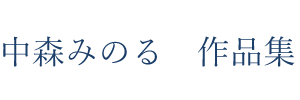第2章 占い師
雪村さんがこっちに駆け寄ってきた。そこにいた多くの人が、何事かと二人の方を見た。
「驚いた! 私たち、おんなじ大学に入ったの? 元気してた?」
「うん」
渡は驚きのあまり、とっさに何をいっていいかわからなかった。
「まさか同じ大学だなんて! しかもこんなところで偶然会うなんて、びっくりだわ」
雪村さんは、渡の顔をまじまじと見た。
「ふーん。背はだいぶのびたんじゃない? でも、それ以外はあんまり変わってないわねえ」
「雪村さんも」
そういうと、ちょっと緊張が解け、笑い出した。
「なに?」
雪村さんがふくれた。
「なんでも。せっかく久しぶりに会ったんだから、どこかで話さない? ——そうだ! 近くに喫茶店があったよ」
「いいわね。でも、喫茶店なんて大人ねえ」
二人はそんなことを言いながら学外へ出た。久しぶりに見る雪村さんは少し背が伸びていて、ぼんやりしている印象がどこか大人びた印象に変わっていた。
大学を左に出た道の角にある喫茶店《ターティ》に入ると、大学生が何人かいた。学生の憩いの場になっているようだ。案内された席に座ると、渡はコーヒーを、雪村さんはショートケーキと紅茶を頼んだ。
「それで、雪村さんはどこの学部に入ったの? 僕は環境学部なんだけど」
「えっ! うそ? 私も環境学部よ。環境科学科」
「僕は生命生態環境科学科。学科までは違ったね」
「はー、びっくりした! でも、目指してる方向は似てるのね。今は一人暮らし?」
「うん。大学近くのマンション。雪村さんは?」
「私も。——もしかして、おんなじマンションだったりして!」
「スリープクローバーってマンションだよ」
「私はハイツフォークロア。じゃ、さすがに違ったのね。ふふ、そりゃそうよね」
「いや、大学が同じっていうだけでもすごい確率だよ! でもまあ、環境学部志望となると、絞られてくるか……。そういえばさっき、サークルに勧誘されてたみたいだけど」
「うん。写真サークルみたい。実は私、今も写真続けてるんだ」
「そうなんだ。僕も時々撮ったりしてる」
「やっぱり続けてくれてたんだ。向いてるって思ったもん、すすめた甲斐があったわ。最近はなにか撮った?」
「うん。動物園にいって何枚か。こんなのとか」
渡はいつも持ち歩いているフォトアルバムを見せた。
「へぇー! わぁ! これいいわねぇ」
雪村さんが、無邪気に写真を見た。渡は懐かしい気持ちになった。
「——あの、モコを連れて行ったおじいさんなんだけど……。探したけど、見つからなかった」
「うん……。連絡がなかったから、そうだと思ってた。大丈夫、きっと元気に暮らしてるわよ」
「そうだといいんだけど」
雪村さんの目に、涙がにじんでいた。悲しさがよみがえってしまったんだろうか。
「おまたせしました。コーヒーと紅茶、それとショートケーキです」
「ありがとうございます」
店員がコーヒーを置く時にまぎれ、雪村さんはハンカチで涙をふいていたが、渡は窓の外を眺めて気がつかないふりをした。
「みてみて! おいしそうじゃない? いただきまーす!」
ショートケーキを食べ始めると、雪村さんの機嫌はすぐによくなってきたので、渡はほっとした。
「……それで、どうするの?」
渡が聞くと、雪村さんはきょとんとした。
「どうするって、なにを?」
「さっきのサークル。入るの?」
「そうね……入ってもいいかなって思ってる。時野戸くんも一緒にどう?」
「えっ?」
思いがけない誘いに、渡は戸惑った。
(写真サークル……おもしろいかもしれない。それに、雪村さんも一緒となると……)
渡は、胸がドキドキするのを感じた。
「それ、ちょっと見せて」
渡は平静を装って、サークル勧誘のチラシを受け取った。さっと目を通したが、内容は頭に入ってこない。
「面白そうだね。新歓コンパにいってみるのもいいかも」
「それじゃ、一緒に行きましょ。今週土曜日の12時から、近くの公園でバーベキューだって。——でも、ちょっと待って! 私たちが知り合いってことは、秘密にしとかない?」
「どうして?」
「だって……冷やかされたりしたら、やりづらいじゃない?」
「確かに。それじゃ秘密にしとこう」
◇
新歓コンパ当日。広い公園でバーベキューが始まった。新入生も15人ほど集まっている。食べるのと自己紹介で忙しかったが、暖かい人の多いサークルだと渡は感じた。先輩は2年生8人、3年生が11人、4年生は8人中3人来ていた。人数がそれほど多くない分、仲良くなれそうな気がした。
「そういえば、この中で恋人がいる人っているの?」
コンパも中盤に差し掛かったあたりで、3年生の女性の先輩、中根さんが突然たずねた。すると、一同ざわめいた。
「あの……私、います。遠距離だけど」
島田 真菜がおずおずと手を挙げた。
「わ! 島田さん恋人いるんだ! 男子のみんなは残念だったね。他の子は?」
コンパに来てた子はみんな首を横に振った。渡は雪村さんを盗み見た。すると、彼女と目が合った。渡は恥ずかしくなって目をそらすと、小さく首を横に振った。雪村さんも、首を横に振っていた。
「えー、そうなんだ。じゃあ、この中でも恋人ができるかもね」
「そうそう。それだけ仲良くなる機会は多いわ! まあ、その人次第だけどね」
わはははは、と笑い声が上がった。雪村さんはどうしたわけか、緊張して縮こまっている。先輩たちの軽口は、普段なら辟易ししてもおかしくないような内容もあったが、不思議と嫌な気持ちにならなかった。雪村さんに彼氏がいないことがわかったからだろうか。
コンパが終わりマンションに帰ると、雪村さんと電話で話した。彼女はサークル活動に乗り気のようだった。確かに、みんなで旅行して撮影会をするというのは一度もやったことがなかったし、面白そうなので入ることに決めた。
大学の授業も始まった。授業内容も、必修以外は自分で選べるので、興味のあるものからどんどん取っていった。いくつかのクラスでは雪村さんと一緒の授業だったため、一緒に授業を受けた。生物や環境に関する授業は、渡が求めていた通りのものだった。ただ、高校とは勝手が違った。大学では、どれだけ能動的に課題に取り組めるのかということが重要なのだと気づいてからは、時々図書館で、授業に出てきた本を読んでみたりするようになった。
サークルの第一回は自己紹介だった。これまでどんな写真をとってきたのか、どんな写真機をつかっているのか? ということを同じ一年生のみんなに紹介する、というのが伝統的な初めの活動ということだった。
渡はこの日のために、地元の写真を除き、動物の写真や旅行先での風景の写真を5枚ピックアップしておいた。写真機は、最初に使っていたデジタルカメラと、後から使いだしたフィルムカメラ両方持ってきている。
新入生の一年生は渡を入れて全員で8名、写真をそれぞれ持ち寄り、サークル棟三階の一室に集まった。
池沢 翔太(いけざわ しょうた)、小松浦 穂乃花(こまつうら ほのか)、間鳴 梶朗(まなり かじろう)、島田 真菜(しまだ まな)、南木谷 十九(なきたに じゅうく)、時野戸 渡(ときのと わたる)、藤未 りお(ふじみ りお)、雪村 まりん(ゆきむら まりん)の8名。
全員でテーブルを囲むと、自己紹介を書き込んだ紙のコピーが配られた。
風景写真をとっている人、人物の写真ばかりを撮っている人、食べ歩きのお店の料理を撮っている人、昆虫を撮っている人、なぜか懐かしい80年代風の写真を撮っている人、こだわりなくいろいろ撮っている人……。
誰が何を撮っているのか、とてもすぐには覚えられないが、一緒に活動するうちに、どういう写真を撮るのが好きなのか、いやでもわかってくるんだろう。学部も違えば出身も違う、さらには好きなものまでバラバラな人たちが、写真という一つの共通点で集まっている面白さがあった。
雪村さんの写真は、いつも見慣れていたせいか、写真の裏の名前を見なくてもすぐにわかった。動物の写真が3枚、風景の写真が2枚だった。
「藤未さんってリンスタやってるの? おいしそうだね」と、間鳴梶朗がいった。
「うん。写真はほとんどリンスタに載せるためにとってるんだ。写真もだいたいスマホだし。そういう間鳴くんは——あ、昆虫の写真ね……。うん、とっても……なんていうか」
「昆虫苦手なんだったら、無理しなくていいよ」と、間鳴くんは朗らかに言った。
「みんなこだわってるのね。私のなんて、散歩の途中でちょこっととったものばっかりだから恥ずかしい。この雪景色の写真なんて、とてもきれい。カラーなのにモノクロみたいだし……誰が撮ったの?」と、小松浦さんが聞いた。
「それ、故郷なんだ。僕だよ。南木谷」と、南木谷十九がいった。
「十九って、珍しい名前だね」と、さわやかな池沢翔太がいった。
「両親が19の時に付き合い始めたからなんだ。へへへ、笑えないジョークみたいだろ? いまじゃ気に入ってるけど」
「いや、かっこいいよ」
「そうよ。私なんか、怪我するたびに、不死身のりおちゃん! って、からかわれたのよ」と、藤未りおがいった。
「それを言うなら、俺のことはカゲロウって呼んでほしいな」と、間鳴がいった。
「どうして?」と、小松浦 穂乃花が聞いた。
「ほら、俺って虫が好きだろ? それで、名前が梶朗。少しもじったらカゲロウになるから、そう呼んでほしいんだ」
「ああ、わかったよ。カゲロウ。南木谷君は、何か気になった写真はあった?」と、池沢翔太が言った。
「僕はこのモノクロの写真が気になった。くまのぬいぐるみのモノクロ写真」と、南木谷がいった。
「それ、あたし……」と、島田 真菜がおずおずと手を挙げた。
「懐かしい雰囲気がよく出てるわね。モノクロでとってもセンスあるわ」と、雪村さんも同意した。
「雪村さんのうさぎの写真も、あの、とっても‥‥‥かわいい」と、島田さんがいった。
「ありがと。池沢くんは人物写真が好きなの?」と、雪村さんが聞いた。
「うん。人物ばっかり撮ってるよ。歩いてる人にモデルになってもらうんだ」
「へえ、すごいな」と渡が言った。
みんなは、どんな写真を撮りたいかとか、どんな写真機を使ってるのかを教えあった。そのあと、学部はどこかとか、出身はどこかという話題になった。雪村さんと渡は出身が同じということで驚かれたが、中学校が同じだったことは伏せておいたし、高校は全く別だったので、そういうこともあるかとみんな納得していた。
「でも、活動どうする? 基本的に自由なんだろ?」と、間鳴梶朗(カゲロウ)がいった。
「二人組とか三人組とか、グループをつくって活動するっていってたけど……それも自分たちで決めていいっていう話だったわよね」と、小松浦さんがいった。
「一人で撮りに行くんなら、サークルに入っている意味はあんまりないかな」と、池沢くんがもっともなことを言った。
「えーでも私、リンスタに載せるやつ撮りに行きたいなぁ。リンスタやってる人いないの?」と、藤未りおが聞いた。
「私、やってるわよ」と、小松浦穂乃花がいった。
「僕も一応アカウントはある」と、渡はいった。
「いや、みんなやってるでしょ」と、間鳴 梶朗(カゲロウ)が笑った。
「あの……私、やってない」と、島田さんがいった。
「え~、もったいないよ。一緒にやらない?」と、藤未さんがいった。
「……うん」
島田さんはそうこたえたものの、どうやらあまり乗り気ではないようだ。
「撮りたいものを撮りに行くっていうのも大事だし、自分のテーマを変えてみるっていうのもおもしろいかもしれないな。だけど、やっぱり合わないことってあるから、無理しなくていいと思うよ」と、池沢くんがいった。
「えー、そんなのつまんない」と、藤未さんが言った。
「でも、藤未さんだって、昆虫の写真撮りにいきたくないでしょ?」と、池沢くんがなだめた。
「……うーん、まぁ」
空気が悪くなりそうなので、渡はあわてた。
「まあ、何を撮りに行くのかはその時々決めたらいいんじゃない? いろんな人の興味にあわせてみたら発見があるかもしれないし。自分ひとりで撮りに行ったらいけないって決まりもないんだしさ」
「確かにな」と、南木谷がいった。
「先輩たちはどうしてたの? 誰か知ってる?」と、雪村さんが聞いた。
「なんか、最初のうちはメンバー入れ替えながら、グループでいろいろ出かけてたらしい。その都度リーダーを決めて、リーダーが撮りに行く場所とか被写体のテーマを決めてたってさ」と、間鳴 梶朗(カゲロウ)がいった。
「じゃあ、ひとまず4人グループを二つ作って、毎回違うところに行くってのはどうかな。メンバーはくじとかで毎回入れ替えてさ」と、池沢くんがいった。
「いいわね。そうだとしたら、初めの何回かは、みんなで行きたいわね」と、小松浦さんがいった。
「確かに」と、池沢くんもいった。
みんながこの意見に同意したので、しばらくみんなでかたまって活動することになった。
初めてのサークル活動は、近くの公園で子供たちを撮った。2回目は、林の中で思い思いの自然を撮り、3回目は食べ歩きと写真の組み合わせだった。似たような風景を撮っているはずなのに、それぞれの写真には個性がでるのが面白かった。人の好みに合わせてみるだけでも、写真との向き合い方や撮り方が変化する。その変化とともに、新たな発見があることに、みんなは少しずつ気がついていった。
渡には、サークル活動とは別の楽しみができた。また雪村さんと二人でいろんなところにでかけるようになったからだ。二人の距離は、以前にも増して近づいたようだった。同時により一層、その関係が壊れてしまうことが怖くなっていた。
しかしそれ以上に、渡が後悔を抱えているのも事実だった。また前みたいになりたくない。
7月。二人で撮影会にいくようになってから2か月ほどたった頃、思いがけず、絶好の機会が訪れた。サークル活動が終わってから、きれいな夜景の見える場所に二人内緒で落ち合って、撮影会をする約束を取りつけたのだ。渡はその日、告白することに決めた。